昨日、フジテレビのココリコミラクルタイプですごい企画を見てしまいました。
その名も「ウィニー女 一斉テスト」
なんでもウィニーの情報漏えい問題にからめて、ウィニー女=情報漏えい女=口軽女なんだそうです。
おもわずメモってしまったので、興味のある方はどうぞ。
■ウィニー女 一斉テスト 全11問
1.耳ダンボになりすぎて仕事が手につかない
2.TPOをわきまえず発言することがある
3.筆談ができない
4.最近話に入れてもらえない
5.よく口止め料を貰う
6.ひとこと多い
7.「正しくは・・・」が口癖だ
8.酔うと記憶をなくす方だ
9.世話好きなところがある
10.ブログに実名が並んでいる
11.言い訳が下手だ
実は、先日アスキーの情報漏えい対策セミナーで講演させてもらったときに、安部官房長官の「ウィニー使わないで」会見以降、これまで主流だった「Winny」という英語での検索に加えて、「ウィニー」というカタカナでの検索が急増しているので、今後は素人の事件がもっと増える可能性があるのではないかという話を紹介したのですが。
なんだか民放におけるウィニーの取り扱いというのは、話題を突き抜けて完全にネタになってしまったようです。
(下記にGoogle Trendsのグラフを参考まで貼っておきます)
■「Winny」の検索数推移
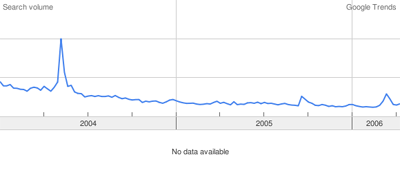
■「ウィニー」の検索数推移

セミナーの前に、平成教育予備校で浅草キッドの水道橋博士が「ウィニーで問題が漏洩してるんですよ!」って発言したのが使われてただけでも衝撃を受けてたんですが。
番組の企画の一つに堂々と使われるようになるとは、完全にウィニーという単語はマスに到達したということでしょうか。
この勢いだと今年の流行語大賞は「ウィニー」か「情報漏えい」あたりが入りそうな雰囲気ですね。
そういえば、冒頭のウィニー女 一斉テストの番組での結果ですが。
2位が同率6点で眞鍋かをりと坂井真紀。
1位が7点の加藤夏希だそうなんですが。
なんでも加藤さんは「ブログに実名が並んでいる」が当てはまるとかで、アップのショットにテロップで「Winny!」とかかれてました。
皆さんもご注意を。
ちなみに、次回は負け犬一斉テストだそうです。
週刊ビジスタニュースにコラムを書きました
ソフトバンククリエイティブが発行しているメールマガジン「週刊ビジスタニュース」にLife Hacksに関するコラムを書かせていただきました。(Kさん、貴重な機会をいただきありがとうございました)
メールマガジンでは切込隊長と速水さんというすごいメンバーに挟まれてるので、かなり恐縮です。
Life Hacksは田口さんが日本で紹介されてからずっと注目していたコンセプトなので、絡んだ仕事ができてうれしいです。(本業とも関係あるので、もっと力を入れていきたいところです。)
VAIO Type Uに見るハードウェアとソフトウェアの可能性
アカデメディアの「デジタルスタイル会議」に参加してきました。
詳細のレポートは参加者の方の皆さんからあがってくると思うので、そちらを見ていただくことにして、個人的な感想をメモしておきます。
今日の目玉は本日発表されたばかりのVAIO Type U。
ちょっと遅れてしまったので全部は聞けなかったのですが、開発者の方から開発経緯だとか製品にかける思いのプレゼンがありました。
ミッキーのファンタジアをイメージしたスティックの操作感や、クリックしたときのアイコンの反応をバビル2世のロデムをイメージしたとか、ソフトウェアレベルの操作感にも深いこだわりを見せておられたプレゼンで、実に楽しそうにプレゼンをされていましたが。
個人的に特に印象に残ったのは、ハードウェア開発の可能性の幅広さ。
自分も仕事ではソフトウェア開発に携わっているわけですが、どうしてもソフトウェアだけの視点で開発を行うと、PCや携帯電話などの端末の制約が最初から頭の中にあるために、必要な機能を検討する段階から現在の端末の仕様を前提とした企画になってしまいがちです。
それがハードウェアも一緒に開発できるとなると、実現できることは実に幅が広くなるんだなーというのが正直なうらやましい(?)感想です。
今回のVAIO Type Uにしても、開発者がこだわっておられることは、WiFiやブルートゥースなどの機能の実装や素材の質感や手触り、スライドのフィーリングまで、実現できることは実に多彩です。
私たちがアイデアを考えるにも、価格さえ無視すれば実現できることはたくさんあって楽しい会議でした。
当然、ハードウェアの開発はソフトウェアとは全く違う難しさや課題があるわけで、誰もが手軽に参入できる分野ではないわけですが。
今更ながらに考えてみると、ソフトウェアとハードウェアが切り離されているのってPC独特の文化。
その関係でどこのメーカーも似たような感じのパソコンが並んでいる印象が強い分野でもありますが。
今後は、ハードウェアと、ソフトウェアやユーザーインターフェースまでメーカーがコンセプトを持って開発する、VAIO Type Uのようなこだわりコンピュータみたいなもののニーズとか重要性って言うのが、もっと増してくるのではないかと思える会議でした。
当日のログがueBLOGで公開されてますので、ご興味のある方はどうぞ
YouTubeを支えているのはやっぱり資金力みたい
YouTubeのネットワークコストは月1億2000万: suadd blogを読んで。
Forbesの予測によるとYouTubeの回線コストは月100万ドルに達しようとしているようです。
100万ドルってさらっと言われると「ふーーん」ぐらいの感じですが、日本円に直すと1億円以上。
今後アクセス数が少なくとも現状維持されれば、年間13億円以上のお金が回線費用に消えていく計算になります。
先日、「YouTubeにみるチープレボリューションの凄さ」なんて記事で、サーバーとかのコストが急激に低下しているからYouTubeのようなモデルが実現できるのかと勝手に想像して書いてましたが、この金額を聞くとちょっと印象が変わってきます。
前の記事に、直也さんと、小飼さんから必ずしも大容量コンテンツだからサーバーのコストが高いとは限らないという指摘を受けたので、サーバー自体のコストはそれほど高くないのかもしれないんですが。
ネットワークのコストだけで年13億円。
従業員が25人だそうですから、一人平均年収400万円と低めに試算しても年1億円。
賃料だサーバー代だとなんだかんだ考えると、年15億円以上の支出はある計算になってしまいます。
4月にSequoia CapitalがYouTubeに800万ドル(約9億円)の投資をして話題になってましたが、この9億円すら8ヶ月程度で食いつぶす計算です。
もちろん、年15億円以上支出があっても、収入があれば問題ないんですが、YouTubeの収益源といえばようやく最近Google Adsense等の広告を掲載し始めた程度で、まだまだそれほど大きな収入の目処は立っていないはずです。
おまけに日本人の利用率が米国なみなんてデータもあるそうですから、米国の広告主からすれば日本人が閲覧している広告の効果は相当低くなるわけで、日本人の違法利用のために回線コストを負担してるみたいな話になってしまいますね。
(日本語ページを提供して日本人向けの広告を取れれば良いのでしょうけど)
この計算だと今年末までには資金調達なり買収なり何かしらの動きがありそうな感じです。
ただ、そういえば、海部さんが先日「再び、Web2.0とインフラの制約に思いを馳せる」という記事で、Flickrを買収したYahooが困り果てているという話を例に出して「なるほど、だからだーれもYouTubeに手を出さないワケだ」と書いていたのを思い出しましたが、確かにこれは買収する側にとっても判断が難しいギャンブルですよね。
はたしてYouTubeは金の卵なのか、年15億円以上の金食い虫なのか。
まぁ、Googleも創業後しばらくはたいしたビジネスモデルが無かったという話ですから、YouTubeもそのプロセスと思えば、ギャンブルとしては悪くないのかもしれませんが。
(個人的にはワーナーと提携して話題になったBitTorrentあたりがP2P技術をうまく活かして、このCGMの分野に出てこれれば面白いのではと思いますが・・・)
それにしても、やっぱりこのスケールのギャンブルができるというのにアメリカの懐の広さというかベンチャーへの旺盛な投資意欲を感じてしまいますね。
日本でも、ソフトバンクとかUSENぐらいなら、この規模の先行投資をするかもしれませんが、ベンチャーキャピタルでこの規模のギャンブルをするのは日本ではなかなかお目にかかれそうに無いですね。
先日、フジテレビが似たようなサービスを始めるといって話題になってましたが、はたしてどういうシナリオを想定しているんでしょうか?
はてなブックマークで売られたケンカは買うべきか?
ekken♂:はてなブックマークに反論が出来ないなんて誰が言ったんだ?を読んで。
最近、はてなブックマークのコメント機能に関して、いろんなところで議論が盛り上がってきているようですね。
上記のekkenさんの記事では、はてなブックマークで言われっぱなしが嫌なら「反論しちゃえば良いじゃないか」とばかりに具体的な反論方法がいくつも解説されていますし、トラックバックでkaienさんが「はてなブックマークのコメントに対して反論しづらいのは、単純にその文章が短いから」ではないかと指摘していたり、赤枕さんが「del.icio.usはツールであることを目指しているのに対して、はてなブックマークはコミュニティであろうとしている」という指摘をしていて、なるほど面白いです。
そういえば、かなり前にHeartligicの小林さんがはてなブックマークのコメントが荒れやすいのを「割れ窓理論」で説明していましたが、確かに荒れているときのはてなブックマークのコメント欄は、書かれた方からすると暴力的に感じることもありますね。
実は、私も一時期はてなブックマークの厳しいコメントに耐えられず、はてなブックマーク恐怖症になったことがあります。
ブログからトラックバックとかで突っ込まれれば、またトラックバックで反論したりとか、そのブログのコメント欄に出かけていったりとか、議論のしようがあるわけですが、はてなブックマークだと一方的に言われっぱなし。
なにしろ、一応1時間とか時間かけて書いた記事を、あっさり「中身が無い」とか「面白くない」とかバッサリきられたら、そりゃショックですしケンカ売られているような気分にもなりますよね。
おまけに、自分自身、叩かれるのに強いタイプではないので、過去の胸に突き刺さるコメントの恐怖が忘れられず、せっかくたくさんの人にブックマークしてもらえたのが分かっても、ブックマークのコメント一覧を怖くて見に行けない時がありました。
(まぁ、そんな愚痴をSix Apartの飲み会か何かでこぼしていたらモダシンさんなら「そんなんならブログやめちまえ」とか言われてしまったわけですが。)
そんな時に考え方を変えるきっかけになったのが、otsuneさんに教えてもらったブラックマジックの話。
詳細は上記の記事を読んでもらえればと思いますが、要は、どんな人でも議論でも一言でバッサリ相手を傷つけることは可能なわけで、そういうコメントを全部まじめに気にしてても仕方がないですよ、と。
まぁ、たしかにそう言われればそうですよね。
ちょうど先日、梅田さんも「総表現社会と村上春樹の言葉」という記事で、批評家の評論は読まないけれど、インターネットの読者の意見を全部読む村上さんの「「誤解がたくさん集まれば、本当に正しい理解がそこに立ち上がる」」という台詞を紹介されてましたが、こちらもなるほど納得です。
どうしても、私たちは個人個人から言葉で攻撃されると反論したくなってしまうわけですが、自分がフィードバックとして受け止めるべきは、一人一人の厳しいコメントとかではなくって、全体としての空気のようなものなのかもしれないなーと思ったりします。
さらにもう一歩、無理矢理アテンション・エコノミーな視点で考えてみると、厳しいはてなブックマークのコメントを残してくれた人も、わざわざ時間を割いて自分のブログを読んでくれた人なわけで、さらにわざわざブックマークしてコメントするほどの時間を割いてくれているわけで。
上記のブラックマジック的な嫌がらせコメントはまぁ置いておいても、それ以外の人はわざわざ貴重な時間を割いてこちらのブログの批評をしてくれているわけですから、厳しい批評にしても誤解から生じた非難でも、売られたケンカではなく、自分を成長させてくれるアドバイスとして受け止めるべきなのかなーと、そんな風に思う今日この頃です。
まぁ、そもそも自分がブログを書いているのは、文章を書く練習だったり、他の人にいろいろ教えてもらいたかったりするわけで、せっかくのブログに対するフィードバックに目を通さないなんて本末転倒な気もしますし。
ということで最近は、なんとかはてなブックマーク恐怖症を克服し、はてなブックマークのコメントをできるだけ「前向きに」全部チェックするようにしています。
■はてなブックマークの批判コメントに対する個人的な心構えはこんな感じ。
・はてなブックマークのコメントを一通り見る
・たくさんコメントがあったら、全体の雰囲気を見る
・全体として厳しいコメントが多かったら、大いに反省する
・一人だけ厳しいコメントだったら、その人の他のブックマークを見る
・他も全部ブラックマジック系だったらスルーする。
・自分にだけ厳しいコメントだったら反省する。
・必要だったら反省を活かして、ブログで前の記事をフォローする記事を書く。
でも、やっぱり胸に刺さるようなキツイコメントを見ると、その日一日凹んでしまったりするので、お手柔らかにお願いします、はい。
ブルー・オーシャン戦略 (W・チャン・キム)
 ブルーオーシャン戦略は、新市場を創造する戦略をテーマとしている書籍です。
ブルーオーシャン戦略は、新市場を創造する戦略をテーマとしている書籍です。
副題に「競争のない世界を創造する」と書かれているように、競争自体を無意味なものにする未開拓の市場〈ブルー・オーシャン〉をいかに創造するかというテーマについて体系だって解説されており、非常に参考になります。
特に個人的に気になったのはブルーオーシャン戦略は「価値を高めながらコストを押し下げる」という点。
一般的にはついつい「価値とコストのあいだにトレードオフの関係が生まれる」と考えてしまいがちですが、差別化と低コストをともに追求するというコンセプトは、興味深いものがあります。
(個人的にはブルー・オーシャンの対義語となるのが、血みどろの戦いが繰り広げられる既存の市場〈レッド・オーシャン〉というのが、なるほど納得という感じでした。)
まぁ、こういった理論については実践できてなんぼというところですから、読んで分かった気になっているだけでは駄目なんでしょうけど・・・
新事業に携わる方には是非お勧めしたい本です。