 ブログやFlickrなど、最新サービスの伝道者として有名なあの伊藤譲一氏が本を出したと聞いたので、早速買ってみました。
ブログやFlickrなど、最新サービスの伝道者として有名なあの伊藤譲一氏が本を出したと聞いたので、早速買ってみました。
伊藤譲一さんにお会いしたことは無いんですが、今の会社に来た初期のころに、飲み会で御手洗さんに伊藤譲一さんがしていたという「素人が作り出した無料のコンテンツの可能性」の話をしてもらい、大いに刺激を受けたという経緯があります。
ただ、書籍を買ってから気づいたんですが、著者に名前が連なっている伊藤さんとTechnorati創業者の執筆部分は2章だけで残りはデジタルガレージチームによる共著。
さらに副題でテクノラティの名前が出ているように、どちらかというとテクノラティを中心としたブログの世界観本という方が正しいようです。
(買う前に気づけという話ではあるんですが)
個人的に本を読んで印象に残ったのはやはり伊藤譲一さん執筆の第一章の部分。
ブログやWeb2.0のような最近のインターネットの盛り上がりというのが、どういうことを背景にしているのかという点を整理して理解することができます。
特に興味深いのは今のWeb2.0は初期のインターネットのころに理想とされていた本来のインターネットに戻ってきているという視点。
もともとはインターネットはオープンなものだったのに、インターネットバブルの時にIT関連企業が大企業化したことでインターネットのイメージが本来と違うものになってしまっただけ、現在はもともとの思想に戻ってきているという指摘はなかなか興味深いものが有ります。
最近、インターネットバブル前に書かれたレポートとかを読んでも、古い感じがしないのはそういうことかもしれません。
mixiが「おしゃべり」の中心になるということの意味
[mi]みたいもん!!: mixiミュージックでいよいよはっきりした、笠原さんは何にも迷ってない。を読んで。
先日のmixiミュージックの開始は、なかなかインパクトがありましたね。
ニュースの追加によるサイトデザインの変更の頃は、結構コアユーザーの反発もあって、どうなることかと思いましたが、ちゃんとその後デザインのカスタマイズができる機能も実装しているあたりも、実にポイント高いです。
最近、mixiがそれほど真新しくなってきたせいもあり、mixiに飽きたとか、mixiはビジネスモデルが古いとかという批判も増えてきたように思いますが、個人的にはいしたにさんが書いてるように、今のmixiはそれこそ何の迷いも無く、ただひたすら成長の道を歩んでいるようにしか見えません。
おそらく、この議論のポイントになるのがmixiをどういう視点で見るかということでしょう。
一般的なビジネス視点で見る人からすると、mixiの利用者層とかオンライン率の高さとか、今のポジションとかから、もっといろいろやれることあるのに何でやらないんだという指摘も出てくるはずです。
実際、個人的にも、もし自分がmixiの社員だったらやってみたいことが山のように思いつきます。
ただ、そういう視点はある意味mixiのエネルギーの源が何であるかを見誤っているのかもと最近思えてきました。
mixiのエネルギー、それはまさに「おしゃべり」だと思います。
しかも、ブログのように姿かたちの見えない人に街頭で叫んでいるような、スピーカー型の演説とか独り言じゃなくて。
知っている人が周りにいるのが確実に分かっている状態でのおしゃべり。
文字通り相手の顔が見えるおしゃべり。
いしたにさんも、笠原さんの「とにかくPVを稼げるサービスを作りたかった」という台詞を引用していますが、ページビューベースのビジネスにおいては、おしゃべりというのは実に強力なサービスです。
実際、ヤフーでもヤフーメールが全体のページビューに占める割合は15%近くあったと記憶してますし、ヤフーメールを使っている人にはヤフーをブラウザのホームページにするための一つの大きな理由となり、重要なツールの役割を果たしています。
おしゃべりのプラットフォームというのは、利用者の最初の入り口にもなれるわけです。
もちろん単純におしゃべりをするならメッセンジャーや電話の方が良いかもしれませんが、mixiが提供しているのはそういうリアルタイムで半強制的なコミュニケーションじゃなくて、メールと同じ非同期のゆったりしたコミュニケーション。
日記を書けば誰かとおしゃべりできるかもしれないし、コミュニティにいけば誰かとおしゃべりできるかもしれないし、ニュースがきっかけにおしゃべりが始まるかもしれないし、音楽がきっかけでおしゃべりが始まるかもしれないし。
一つ一つのおしゃべりにはビジネス的価値はほとんど無いかもしれませんが。
笠原さんが以前から言っているように、mixiがメールに次ぐ新たなコミュニケーションのプラットフォームになれれば、それこそがmixiの存在意義になるわけで、それって真剣に凄いことです。
もちろん、おしゃべりの場だけじゃなくてもっといろんなことができればビジネスとしては儲かるかもしれませんが、現在のmixiの最重要課題は何と言っても急増する利用者をいかにさばいて安定してシステムを動作させるかという点。
そのあたりは、湯川さんの笠原さんインタビューでもはっきり書かれています。
何しろ、おしゃべりの場で気軽におしゃべりができなくなったら、それはおしゃべりの場ではないわけで。
いくら便利な機能がいっぱいあったとしても、利用者はみんな逃げてしまうでしょう。
甲斐さんが書いているように、mixiミュージックについては「サービス自体はLast.fmであり音ログであってそこまで目新しいものではないけど、日本で最もアクティブなユーザーを抱えるmixiで始まったのが大きい」わけで、mixiがおしゃべりの中心にいるからこそ、同じような音楽連携サービスでも利用者の盛り上がりがまったく違うわけだと思います。
そういう意味でも、今はとにかく安定稼動に注力して利用者のインフラになるための努力を日々続けることが重要なわけで、新サービスはあくまでおしゃべりのネタ提供というところでしょうか。
いろんな手段で儲けるのはその先でも十分間に合いそうな感じです。
Eメールにおける最近のスパムメールの増え方を考えると、大事なメッセージはmixiで送るという未来が来てもおかしくない感じもしますから、以前書いたようなmixi会員3000万人という未来があっても不思議ではなくなってきた気がします。
もし、mixiに死角があるとしたら、クローズドなパソコン通信のニフティのフォーラムが、オープンなインターネットの登場によって勢いを失ったように、クローズドなままのmixiがオープンなおしゃべりサービスによって勢いを失うかも、というぐらいの感じでしょうか・・・?
なんにしても、今後のmixiの動向からやっぱり目が離せそうにありません。
(甲斐先生、こんな感じで良いでしょうか?)
鳥越俊太郎は日本に市民記者文化を作れるか
livedoor ニュース – 鳥越俊太郎氏、初代編集長にを読んで。
あの鳥越俊太郎氏がオーマイニュース日本版の編集長に就任するようです。
オーマイニュースについては、ソフトバンクの資本参加が決まってから編集長が誰になるか注目していたのですが、結構驚きのニュースですね。
人によっては鳥越さんにネットのことなんて分かるのかといぶかる向きもあるかもしれませんが、韓国のオーマイニュース自体が自称ネット音痴だった呉連鎬代表によってスタートしていますから、そこはあまり呉連鎬代表も気にしていないようです。
特に個人的にはオーマイニュースはとかく「韓国の」という枕詞がつくのが一つの課題だと思っていましたから、知名度の高い鳥越さんを持ってくることで「鳥越俊太郎の」ニュースサイトというイメージを作ることができれば最初の関門はクリアというところでしょうか。
オーマイニュース日本版のチャレンジは、日本でも市民記者という文化なり盛り上がりを作ることができるかでしょうが、鳥越俊太郎編集長であれば、話題性はありそうですから、ある程度の市民記者を集めることはできそうな感じもします。
ただ、やはり気になるのは記事の質の問題。
FPNを運営していても思いますが、JANJANにしろ、ライブドアPJニュースにしろ、投稿型ニュースサイトというのはどうしても読者の期待に対して、記事の質を揃えるというのが難しい課題になります。
オーマイニュースやJANJANのような投稿型ニュースサイトは、市民参加型ニュースサイトと呼ばれることも多いため、そのイメージは比較的素人ニュースサイトに近いイメージで、読者もそういうものだと思って読んでいるところはあるのかもしれませんが。
うがってみれば、オーマイニュース日本版が鳥越さんを看板にしたことによって、読者がニュースサイトに鳥越品質を期待して読みに来るようだと、著名ジャーナリストを看板にしたことがかえって逆効果になるというシナリオも考えられなくもないような気もします。
まぁ、そもそも2ちゃんねるのひろゆき氏なんかは、そもそも「市民メディアは構造的にマスメディアに勝てない。ならばやらないほうがいいと思う」なんてばっさり切っていたりしますから、もっと根本的な部分の議論が先かもしれませんが。
なんにしろ、ソフトバンクがバックについてることですし、まだまだ隠し玉があるかもしれませんから、8月のスタートを楽しみにしたいと思います。
ちなみに、意外に各ニュースサイトで、このニュースの取り扱いが薄いように思えるのは私の気のせいでしょうか?
各メディアがオーマイニュース日本版を注目しつつもあえて流しているのか、ただ単に気にしていないだけなのかも気になるところです。
アメリカではいよいよ電話サービスも無料化が始まるらしい
スカイプ、米国とカナダで「SkypeOut」の無料キャンペーンを実施 – CNET Japanを読んで。
先日、スカイプが米国でスカイプアウトを無料にするというニュースが話題になっていました。
日本の利用者からすると、アメリカ限定じゃなくて日本でも無料にしてほしいと思うところだと思いますが、どうやらアメリカ限定というのが味噌のようです。
あきらかにこの無料サービスのきっかけとなっているニュースがこれ。
AOL『AIM』ユーザーに無料の電話番号を提供する新サービス
日本ではほとんど話題になりませんでしたが、これは大きいニュースです。
AOLというとどうしても日本では認知度が低いのでネット界での影響力も軽視されがちな印象があるんですが、アメリカのメッセンジャーに占めるシェアはいまだにAOLメッセンジャーが4000万人でシェアトップ。
それに対してスカイプは600万人。
そんなAOLがスカイプインにあたる電話番号取得サービスAIM Phonelineを、利用者に無料で提供し始めたわけですからインパクトは大きいです。
しかもこの電話番号取得サービスは、ボイスメールも無料でセット。
つまり、スカイプが、スカイプアウトと並ぶメインの収益源にしているスカイプインとボイスメールという有料サービスを無料で提供してしまうわけです。
(以前、スカイプカンファレンスで講演させていただいたときには、Googleが無料でやるんじゃないかと予想してたんですが、残念ながら外れですね。まぁでもGoogleもAOLに10億ドル投資して、Google TalkとAIMの相互乗り入れもあるのではという話なので当たらずとも遠からずということで。)
スカイプインもボイスメールも無料というとすごい話に思えますが、実際にはスカイプインを一年契約しても支払いは5000円程度ですから、IMの利用者を一人獲得するのにかかる広告費を考えると、この規模の事業者にとっては実は安い経費なのかもしれません。
まぁ、こうなってくるとまさに体力勝負ですね。
スカイプもeBayがバックについていますから、当然黙っているわけも無く、今回の対抗策となったようです。
この戦いがどこまで飛び火するのかは良く分かりませんが、何しろAOLグループとeBayグループというトップクラスのネット企業の戦いですから、いよいよ電話サービスも、Hotmailやインスタントメッセンジャー同様、利用者獲得のための無料サービスという扱いになってくる可能性も十分ありそうな感じです。
そう考えると気になるのは、日本でこの手法を取ってくるのは一体誰かということでしょうか。
順当に考えるとソフトバンクグループのYahooメッセンジャーというところですが、どうなることか・・・
AERA5月29日号にコメントが掲載されました。
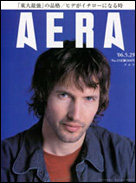 AERA 2006年5月29日号のウィニー特集のコラム「安部長官のウィニー自粛要請で、逆に利用者が増加?」で、コメントを紹介していただきました。
AERA 2006年5月29日号のウィニー特集のコラム「安部長官のウィニー自粛要請で、逆に利用者が増加?」で、コメントを紹介していただきました。
このブログを読んでいる方であれば、覚えがあるかもしれませんが、過去に書いたウィニーの検索数グラフの話がらみです。
この問題はいろんな議論軸があるので、非常に難しい問題ですが、これをきっかけに日本のソフトウェア業界が良い方向に行くことを切に願います。
見える化-強い企業をつくる「見える」仕組み (遠藤 功)
 最近、話題になっている「見える化」の本です。
最近、話題になっている「見える化」の本です。
会社のブログで、見える化のまとめ記事を書いたのですが、こちらにも読書メモを書いておきます。
書かれていることは非常に基本的な話ではあるのですが、改めて具体的に自分の身の回りに落として考えると、実はこういう視点で自分が仕事をできていないというのを痛感させられる本です。
個人的に非常に印象に残ったのは、IT偏重による落とし穴。
自分自身、システムやソフトウェアで企業やビジネスマンの生産性向上をするというのが目的なわけですが、どうしてもソフトウェア会社なだけに手段をPC等のIT手段に頼ってしまいがちです。
本質的には問題の改善ができれば良く、何もかもIT化する必要は無いわけで、そういう意味では、はてなのようにデジタルの先端にいるようで意外に仕事をアナログに処理している会社っていうのは正しいなぁと思ったりします。