今日から始める! Web 2.0超入門講座 ~初心者でもよくわかる「これからのWeb」のすべて~を読んで。
ちょっと前の記事になりますが、INTERNET Watchで、heartlogicの小林さんが「Web 2.0を実感するために、ユーザーが経験すべき10のこと」の改訂版記事を書かれていました。
確かに、このリストをこなしていけば、なるほどWeb2.0を実感できそうだという良いリストになっています。
まだ見てない方は是非読んでください、お勧めです。
ちなみに、このリストを改めて眺めていて個人的に思い出したのが昔書いた世代論の話。
そもそも、当時ブログ三日坊主の繰り返しだった自分が、継続して真面目にブログを書くようになったのは、いまでいうところのWeb2.0的な世代と知り合うようになって、自分とその世代の間の意識の差に気づき「このままじゃネット世代に置いていかれる!」と、ある意味恐怖したのがきっかけです。
あれから、2年。
自分としてはかなり努力してWeb2.0的な人たち、ネット世代な人たちに追いつこうとしてきたつもりですが。
やっぱり、自分ってWeb1.0的だなーとか、PC世代だなーと思ってしまう瞬間があります。
そんなわけで自戒の念もこめて、小林さんの真似して「自分はやっぱりWeb1.0な人間かも、と思う瞬間」をリストにまとめてみました。
その1:mixiの足跡機能がどうしても気になる
やっぱり、自分の行動が記録されるという感覚にどうしてもなれることができません。おかげで、気軽にmixi内を見て回ろうとできない自分がいたりします。
仕事中にmixiにログインするには、当然かなりの勇気が必要です。
(これがモバイルだと意外に気楽に見て回れたりするのですが)
その2:会社のブログと個人のブログは当然別物
U30世代の人たちは会社のブログと個人のブログが一体化している人が多いようですが、自分はどうしても感覚的に仕事モードとプライベートモードを一緒にすることができず、会社のブログと個人のブログを、別々に立ち上げてしまいました。本音と建前がある人間ということでしょうか・・・
(まぁ、会社でも個人でもブログを持っている方が変という話もあるんですが)
その3:チャットソフトを仕事中は落としてしまう
もちろんチャットソフトは仕事でも便利ではあるんですが、どうしてもチャットが入るとすぐに返事をしなければいけない錯覚に襲われるので、苦手です。
おまけにプレゼンス情報を知られるのも、なんとなく苦手なので、ついついチャットソフトは落としてしまい、起動するのをそのまま忘れたりします。やっぱりメールが一番です。
その4:タイムリーにブログの記事がかけない
自分の筆が遅いのと、考えがまとまるのに時間がかかるせいもあり、他のブログがもりあがっている話題に一周遅れで参加している自分がいます。
もちろん、参加したイベントのレポートを当日に書くなんて絶対無理です。
その5:タイムリーにトラックバックもできない
その4の延長ですが、せっかくトラックバックをもらっても、返事を考えている間に、その人のブログが他の話題に移っていて、今更感を感じてしまいトラックバックで上手く議論できたことがありません。
でも、スパムトラックバックでも喜んでしまう自分がいます。
その6:ソーシャルブックマークはプライベートモードで使ってしまう
せっかくソーシャルブックマークを使っても、自分がクリップした記事一覧を見られるのが何となく恥ずかしいので、ついついブックマーク一覧を非公開にしてしまいます。
それなら、ソーシャルブックマーク使う必要ないじゃん、と言われても当然反論できません。
その7:Flickrは写真のバックアップスペースとして使っている
実は、背伸びしてFlickrの有料アカウント契約をしていたりするんですが、過去の旅行の写真を一通り放り込んで満足してしまい、Flickrの醍醐味らしいソーシャルな機能とか、ブログとの連携機能とかほとんど使いこなせていません。
これだったら有料ストレージを契約して、そこにコピーしても一緒だったのではと思ったりします。
その8:mixiコミュニティよりMLの方が便利と思ってしまう
最近、何かとクローズドな活動でもmixiのコミュニティが使われる機会が増えているのですが、それなら別にメーリングリストにすれば良いのに、とつい思ってしまう自分がいます。
mixiのコミュニティにメール配信機能をつけて欲しい今日この頃です。
その9:Podcastingの録音が始まるとめっきり無口になる
ブロガーの集まりや飲み会で、最近よくいきなりPodcastingの収録が始まることがあるのですが、ICレコーダーのスイッチが入った瞬間に超無口になってしまう自分がいます。
おしゃべりは好きなはずなんですが・・・・あの恐怖感というか真っ白感というのは何なんでしょうか。
録音中は話を私に振らないで下さい。
その10:いまだにWeb2.0が何か説明できない
はい、致命的です。
とりあえず、その6のソーシャルブックマークだけは、最近公開するようにしてみましたが、果たしてそれ以外の壁を乗り越えられるのはいつになるのやら・・・
(そもそも、リスト自体がWeb2.0にほとんど関係無いのでは?という説もありますが)
自分がWeb2.0に慣れた頃にはWeb4.0ぐらいになってそうで心配です。
AERAに取材してもらいました。
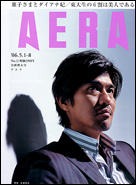 AERA 2006年5月1-8日合併増大号の「アルファブロガーって何だ」という記事にインタビューしていただいたコメントが掲載されました。
AERA 2006年5月1-8日合併増大号の「アルファブロガーって何だ」という記事にインタビューしていただいたコメントが掲載されました。
(mさん、ありがとうございました。)
まぁ、私は無難なコメントをしているだけなのでスルーしてもらえればと思いますが、記事自体はライターの松田さんが、コグレさん、橋本さん、磯崎さん、R30さん、きっこさんの5名にインタビューを実施され、それぞれのブロガーの方のお勧めブログを掲載したりと、多面的にブログの動向をカバーした記事になっています。
AERAのような硬派な雑誌に、ブログについて、しかもアルファブロガーについて取り上げていただけるとは、投票企画を企画した甲斐があったものだと、ひとりでしみじみと勝手な感慨にふけっていたりします。
記事を読んで、またブログに興味をもってくれる人が増えると良いですね。
やっぱりライブドアの技術力は結構すごいらしい
ライブドア、新RSSリーダー「livedoor Reader」ベータ版を公開 – CNET Japanを読んで。
livedoorから新しいRSSリーダーがリリースされました。
最初ニュースを見たときは、あれ?ライブドアってBlogリーダーなかったっけ?とか思ってたんですが、どうやら完全にゼロから作り直した模様です。
宮川さんがブログでべたぼめしてたので、試しに使ってみたのですが、確かに凄いです。
デザインもお洒落な感じですし、操作性やレスポンスも良い感じ。
一通り欲しい機能は揃っていますし、レートを使ったフィードの段階評価やピンによるまとめ読み機能など、気合入ってます。
私は個人的に相変わらずBloglinesを使い続けているんですが、これは乗り換えを真剣に考えさせられる一品です。ただ、ライブドアはいつものIDを取り損なっているのが微妙なんですが。
(ちなみに、処理中のときに人のアイコンが走っていて、失敗するとorzっぽいアイコンになるあたりのセンスを見るかぎり、最近入った最速の人が関わっていそうな感じですがどうなんでしょう。)
ライブドアショック後、ひとしきりマスメディアから虚業だ何だとバッシングを受けていたライブドアではありますが、以前にITmediaで「こんな時だからこそ安定したサービスを」という記事でも描かれていたように、実は急増するトラフィックを淡々とこなしてきた技術者集団でもあります。
インスパイア系のサービスが多いイメージもありますが、livedoorフレパがGREEのユーザー数を超えたなんていう話があるのを見る限り、ライブドアショック後もあいかわらずlivedoorIDの登録数は伸びているようですから、今回のlivedoor Readerのような良いサービスを継続して生み出すことができて、USENとの良いコラボレーションができると、案外早くに輝きを取り戻すことができそうな気もしてきます。
お蔵入りになった球団名「ライブドアフェニックス」のごとく、新生ライブドアがライブドアショックから不死鳥のようによみがえることができるのか、注目したいところです。
グーグルは、破壊者か、全能の神か
 [R30]: 書評:「グーグル 既存のビジネスを破壊する」を読んで。
[R30]: 書評:「グーグル 既存のビジネスを破壊する」を読んで。
すでに、多くの濃いブロガーの間で書評と議論が展開されていますが、私も話題の「グーグル 既存のビジネスを破壊する」を発売前に読ませていただくことができましたので、自分なりの感想を書いておきたいと思います。
書籍についての具体的な書評は、冒頭のR30さんをはじめとする論客にお任せするとして。
個人的な率直な感想としては、この書籍「グーグル」は現在のGoogleの立ち位置を、自分の中で整理するのに非常に役に立つ本でした。
この数ヶ月、自分なりにずっと引っ掛かっていたのは、書籍の帯にも使われている「Google、破壊者か、全能の神か」というような議論。
昨年、自分でも「Googleはネット世界の創造神なのか破壊神なのか」とか「Googleが次に破壊する市場はどこか」とか、Googleの破壊を意識した記事を書いたことがあります。
Googleがあくまで一企業である以上、そういった神学論争的な議論をしても意味がないのは分かっているつもりではいるのですが、そういう議論をしたくなるのがGoogleという会社の特徴でもある気がします。
今回、佐々木さんの「グーグル」を読んで改めて思うのは、Googleを中心としたネット企業が巻き起こしている、富や情報や既得権の再配分の規模の大きさ。
既存の大手マスメディアから、駐車場やメッキ工場まで、これまでの価値感を逆さにしてしまうような規模で、これまでの「持てる者」からこれまでの「持たざる者」にパワーのシフトが起こっている感覚があります。
当然、そんな規模のパワーシフトは、持てる者であった既存事業者からすれば破壊にしか見えないわけですが、持たざる者だった小規模事業者や個人からすれば、新たなビジネスチャンスの創造と言えるわけで。
Googleを中心としたインターネットの未来についての議論が専門家の間で空回りしやすいのは、こういったパワーシフトのどこに自分がいるかで、それに対する視点が全く異なるからというのも大きい気がします。
まぁ、どうも達観している人からすると、この辺りのパワーシフトの議論というのは本来はインターネット自体がもたらす変化として10年前に議論されていたビジョンだったようですので、ようやく本格化したというところでしょうか。
そういう意味では、Googleもインターネット全体の中の一企業でしかないわけですが、そのインターネット時代の新しい価値感を体現する象徴として、Googleが実際の力よりも(期待と不安をこめて)大きく捉えられていて、神扱いされやすい感じもしないでもありません。(佐々木さんは司祭という表現をしていましたが、なるほどという感じです。)
ちなみに、そんなことを考えていて改めて気になるのは、今後Googleの立ち位置はどう変化するのかという点。
極端な例で例えてしまえば、躍進する過程のGoogleのポジションは、民衆から搾取することで大金を稼いでいた悪代官から富を奪い既存の秩序を破壊することで、民衆に富を還元している弱きを助け強きをくじくロビン・フッドやねずみ小僧のようなもんです。
そういう意味では、Googleが利用者から人気があって、既存事業者から煙たがられるのは当たり前かもしれません。
ただ、そのロビン・フッドが統治者の側になったときに、果たして民衆である利用者はどういう反応をするのかというのが個人的には気になります。
やれBMWやサイバーエージェントがGoogle八分にあったという話であれば、まだまだ強いもの叩きで盛り上がれるわけですが。
書籍に書かれていたような、Adsense狩りにあってアカウントを問答無用で抹消されたとか、自分のサイトが検索ロジックの変更で検索上位から消えてしまったとかいう話が頻発してくると、Googleに対する改革者としての期待が、統治者への不満や不信のようなものに変わってしまう可能性は十分あるわけで、改革者のポジションがいつのまにか統治者のポジションになってくることは十分考えられます。
その時に、Googleはどこまで今のビジョンやブランドや立ち位置のようなものを維持することができるのでしょうか?
まぁ、もちろんまだまだGoogleの「強い者叩き」の対象となる企業はたくさんありますから、まだまだしばらくはGoogleはロビン・フッドのポジションでいられるでしょうし、そもそも日本のインターネット市場の統治者はヤフーですから、また議論は全然別になってくるんだと思いますが。
なんにしても、ここ数年のGoogleやそのライバルたちの動向からは目が話せそうにありません。
それにしても、最近ブログで書きたいことはたくさんあるのに、持ち前の筆の遅さも手伝って、全ての話題に乗り遅れている感がある今日この頃です。
ということで、濃い書評を読みたい方はこちらをどうぞ。
・すべてを一度懐疑していく (404 Blog Not Found)
・書評「ウェブ進化論」と「グーグル Google」。そしてメディアビジネスの競争構造の変化。 (FIFTH EDITION)
・書評:「グーグル 既存のビジネスを破壊する」 (R30::マーケティング社会時評)
・「グーグル Google 既存のビジネスを破壊する」佐々木俊尚 (ガ島通信)
 |
グーグルGoogle―既存のビジネスを破壊する 佐々木 俊尚 by G-Tools |
Life Hacks Press で GTDを学ぶ
 Life Hacks Pressは、日本のLife Hack(ライフハック)第一人者である百式の田口さんが、濃い執筆人を集めて執筆したライフハック専用ムックです。
Life Hacks Pressは、日本のLife Hack(ライフハック)第一人者である百式の田口さんが、濃い執筆人を集めて執筆したライフハック専用ムックです。
発売当日に読んだんですが、会社のブログにメモを書いたっきりで自分のブログに感想を書くのを忘れていたのでメモしておきます。
やはり、このムックのお勧めは何と言っても田口さん執筆のGTD特集です。
GTD(Getting Things Done)自体は、以前に読書メモも書いた「仕事を成し遂げる技術」というタイトルで日本語版の書籍も出ているのですが、田口さんは以前からこの本が原書に比べて読みづらいというのを嘆いていました。
そういう意味でも、書籍を読まなくてもこのムックの特集を読めばGTDのポイントは大体抑えることができる濃い特集になってます。
それ以外にもGoogleの活用術から、プレゼン術やマインドマップ、ブログやソーシャルブックマークの活用法など、いま注目の技をまとめて読むことができますので、お買い得の一冊です。
無線LAN共有サービスのFONがインフラただ乗り論に火をつけそう
ITmedia News:個人の無線LANを開放、世界中を“サービスエリア”に──「FON」が日本進出を読んで。
GoogleやSkypeが出資をしたというので話題になった無線LAN共有サービスのFONですが、4月11日に日本参入を発表しましたね。
Skypeは利用者のPCを活用することで、電話交換機網的なネットワークをインターネット上に形成し、無料の電話サービスを実現しましたが。
この無線LAN共有サービスのFONは利用者の無線LANをお互いに利用しあうことで、利用者が無料で利用できる面的な公衆無線LANサービスを実現することを目指しているサービスです。
無料の公衆無線LANサービスと言えば、バッファローが中心に取り組んでいるフリースポットというサービスがありましたが、フリースポットがどちらかというと店舗等の集客目的なのに対し、FONはあくまで利用者同士の協力によるオープンソース的なプロジェクトです。
何でも、昨年11月にスタートしてから、すでに144カ国に2万9000人が登録をしているとか。
まぁ、この数字だけ見ても果たして流行っているのかどうなのかはイマイチ判断できませんが、日本国内の登録者は46人との事なので、これから始まるというところでしょう。
(ちなみにフリースポットは、すでに3663拠点あるようです)
公衆無線LANサービスと言えば、ヤフーやライブドアがサービス展開をしているもののイマイチ盛り上がらない鬼っ子サービスと化していますが、FONの場合に気になるのはサービスが流行るかどうかということよりも、やはり「インフラただ乗り」問題の行方でしょう。
すでにUSENが展開する動画配信サービス「GyaO」やIP電話サービス「Skype」のトラフィック急増をきっかけに、通信会社の経営陣からよく発言されるようになっているインフラただ乗り論ですが。
このFONの場合は、通信会社からするとインフラ自体を勝手に共有されてしまうわけで、GyaoやSkypeのようなアプリケーションよりも、さらに神経を逆撫でされるモデルです。
もちろん、現状のFONのモデルはあくまで他人のアクセスポイントに無料で接続するには自分のアクセスポイントを無料で開放する必要があるので、FONのおかげで回線契約者やISP契約者が激減するという話では無いのですが、まぁやっぱり自分のインフラを勝手に共有されてしまうのは気に入らない話でしょう。
また、Rauru Blogによると、バックボーン網の負荷がより深刻な問題になるのではという懸念もあるようですし、そもそも、ISPの規約上、利用者は勝手に自分の回線を他人に提供してはいけないのではないかという話もあるようです。
まぁ、デジタルガレージの伊藤譲一さんなんかがバックアップして日本参入を発表しているぐらいですから、どこかのISPとある程度水面下で話がついているのかもしれませんが・・・
注目したいと思います。