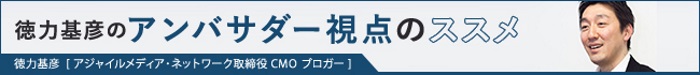このたび、Yahoo!ニュース個人に場所を頂きまして、ブログ記事の一部を寄稿させて頂くことになりました。
ただでも、ブログの更新が滞っているのに、Yahoo!ニュースの寄稿なんて続くのか?と思って長らく挑戦しようとしていなかったのですが、比較的自由な執筆サイクルで良いとの寛大なお言葉を頂いたので、思い切って挑戦させて頂いた次第です。
コラムのタイトルとなっている「ネットコミュニケーションの視点」は、もともとこのtokuriki.comのブログにつけていた名称です。
今はカテゴリの名称にしてしまってますが、この機会に昔のようなニュース考察系のブログを再開してYahoo!に寄稿してみようと復活させてみました。
で、実は、Yahoo!ニュース個人に場所をいただきたいと思った背景が、今回の1本目の記事である「五輪エンブレム騒動に私たちが学ぶべき炎上対応4つの基本」になります。
五輪エンブレム騒動は、横目で見ながら本当に日々悲しく感じていたのですが、ブログで書いたところでたいしてインパクトないだろうし、とか、表で書くとバッシングされそうだし、と悶々としていたところ。
深津さんのエンブレムデザインについての記事を拝見して、やっぱり自分が思っていることを、ちゃんとできるだけ多くの人に読んでもらえる可能性が高い場所に書いた方が良いのかもしれないと背中を押されて、Yahoo!ニュース個人の門をくぐった次第です。
お陰様で寄稿開始のご祝儀だと思いますが、光栄なことになんとYahoo!トピックスにも取り上げて頂いたようで、たくさんの反応を頂きました。
正直、五輪エンブレム騒動についての自分の意見を述べたことで、Yahoo!ニュース個人に場所を頂いた目的をすっかり達成してしまった上に、期待値が随分と上がってしまったので、今後はもう二度とこのピークを越えられないんじゃないかという確信を持ってしまったりしていますが。
ブログの延長として気長に寄稿を続けさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
なお、一応ブログの方にロゴに残すという趣旨で、Yahoo!ニュース側に寄稿した内容をコピペして投稿しておきますが、画像等はYahoo!の方に入っていてその方が読みやすいのでそちらで是非どうぞ。
五輪エンブレム騒動のもやもやが全く消えない今日この頃、皆さんはいかがお過ごしでしょうか?
個人的には一人の日本人として、素直に2020年のオリンピックを楽しみに待っていたかったのに、新国立競技場に、五輪エンブレムに、とまさかの白紙撤回が続くこの状況に、なんとも複雑な感情を抱かざるを得ません。
特に今回の五輪エンブレム騒動においては、炎上対応における典型的な悪手が続けざまに繰り出されてしまった結果、騒動の当初、デザインの専門家からすれば特に問題の無かったはずの五輪エンブレムが、結果的に白紙撤回されてしまうという異常事態になりました。
これにより、一般人にとっては「ロゴが似ていたら撤回するのが当然」という印象を与えてしまう結果となっています。
先日東京都が発表したロゴに対しても早速同様の横やりが入ってしまったようですし、類似の炎上騒動は五輪以外のところにも飛び火してしまっています。今後、新ロゴを発表する全ての企業が同様の洗礼を受ける可能性が高くなってしまったわけで、今回の騒動はこれからの東京オリンピックどころか、今後の日本産業全体にとって大きな禍根を残してしまった出来事として歴史に残る可能性すらあります。
新しいエンブレムについてもこれから公募が始まるレベルでまだまだ騒動が無事に落ち着くかどうかは予断を許さない状況ですが、せめて今回の騒動から、学ぶべき所を学び、今後同様の騒動が起こった際に今回のような最悪の結果にならないために、実際に自分達が同じような状況に追い込まれてしまったらどうするべきか、という観点で今回の騒動を振り返ってみたいと思います。
(なお、以下文章においては東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会を組織委員会と省略して記載しています。)
今回の炎上騒動が最終的に最悪の結果になってしまった背景には、炎上対応の失敗例の典型である4つの要因が存在すると考えています。
■初動の遅れは取り返せない
■炎上原因の誤解がさらなる炎上の火種に
■メディア対応における逆ギレは致命傷
■責任者の不在こそが最大の問題
一つずつ解説しましょう。
■初動の遅れは取り返せない
まず、大抵の大炎上事例で必ず言われるのがこの「初動の遅れ」です。
今回のエンブレム騒動の初期の出来事を時系列に振り返るとこうなります。
7月24日エンブレムが発表
7月27日オリビエ・ドビ氏がFacebookやツイッターで類似性を指摘、ネットで話題に
7月29日ドビ氏の法的対応検討が各種メディアで話題に
7月31日ドビ氏側が使用停止を求める書簡を送付
7月31日佐野氏側は組織委員会を通じてコメントを発表
8月3日書簡の到着がニュースに
8月5日第1回釈明会見
29日に法的対応の検討についての報道があってから、佐野氏側がコメントを発表するまでは中1日。
27日に類似性の指摘が話題になってから実際には3日以上沈黙を貫いていたという印象を持たれてしまったのが、まず大きいです。
佐野氏がソーシャルメディアアカウントを削除していた関係で、余計な憶測をされてしまったのも疑惑を大きくしているようですが、さらには、類似性の問題について報道されてから会見まで1週間も間が空いてしまっているというのはかなり問題です。
背景には佐野氏の海外出張が重なっていたことが影響しているようで実に不運だったと言えますが、31日に発表されたコメントでは詳細が説明されておらず帰国後に会見して見解を表明すると簡単なコメントを発表しただけだったため、疑惑が疑惑のまま憶測を呼び、5日の記者発表会まで話題が広がる結果となっています。
今回の騒動にとってはこのタイムラグは致命的でした。
その間にネット上は様々な憶測が広がりましたが、メディアの記者の方々も明らかにそれらの発言に目を通してから記者会見に望んでおり、それらの憶測を前提とした質問が次々に飛び出す形となっています。
例えば炎上鎮火の成功事例として知られるUCCのケースでは、炎上騒動が発生したその日の夕方にUCC側が謝罪のプレスリリースを出したことで、逆にツイッターユーザーが感心する、という結果になりました。
参考:見事な“鎮火”はなぜ可能だったのか UCCの事例から考えるTwitterマーケティング
ネットの炎上においては沈黙は事実の肯定と受け止められがちです。
当然、企業側が炎上に対して反応することによって、より炎上の事実を多くの人に知らしめてしまうというデメリットはありますが、炎上や疑惑が大きくなれば大きくなるほど、ちょっとやそっとの反論では信じてもらえなくなってしまいます。
逆に言えば、もしドビ氏による類似性の指摘に対して、組織委員会や佐野氏側が早期に否定するなり、直接ドビ氏とのコミュニケーションを取って和解をすることができていたら、ここまでの炎上にはならなかったかもしれないということも言えるわけです。
■炎上原因の誤解がさらなる炎上の火種に
ただ今回の五輪エンブレム騒動において、騒動の方向性が炎上拡大に向かってしまった最大の原因は、おそらくこの問題の火種の背景に対する誤解でしょう。
組織委員会は、問題の根本は当然「エンブレムが似ていること」だと認識されていたと思いますが、実はこの段階で炎上の原因となっている根本的な問題は、新国立競技場問題から続く、「オリンピック組織委員会全体への不信感」にありました。
この炎上原因に対する認識のズレが、さらなる炎上を招く結果となります。
8月5日の釈明会見においては、終始デザインにおける法的・技術的な視点を軸に、ドビ氏側の使用停止要求に対する防衛的な説明が行われます。当然、問題の発端はドビ氏側の使用停止要求にあり、それに対して法的見解から回答するのは法的には当然のことです。
ただ、重要なポイントは既にこの時点では、この問題は単なる法的な問題では無く、新国立競技場問題から続く組織委員会の不祥事として、国民的関心事である報道対象になってしまっていたという点です。
つまり、国民が求めているのは度重なる不祥事に対するお詫びの言葉であって、この際技術的な細かい説明は役に立たない状況に陥っているわけです。
当時、このデザインの類似性に対するドビ氏側の要求は、ドビ氏側が商標登録等を行っていなかったため、業界の常識としては日本側に分があるというのが一般的な見方でした。
そのため、会見の雰囲気としてもどちらかというと佐野氏をはじめ組織委員会関係者はドビ氏側に対する困惑や不信感を表明していた印象を受けています。
ただ、実はこれは国民的関心事になっている記者会見の場においては、登壇者から発せられるドビ氏に対する困惑や不信感が、メディアや視聴者に向けられていると誤解されるリスクがある行為です。
実際、もし新国立競技場問題がなければ、今回の五輪エンブレム騒動が冒頭からこれだけ注目されることはおそらくなかったでしょう。
そういう意味では佐野氏側には非常に不幸な環境になってしまっていたという現実はあります。
ただ、逆に言うとその現実を踏まえずに、法的・技術的釈明会見を行ってしまったのは明らかに失敗です。
事前に組織委員会に対する疑惑や憶測の印象を強く受けていた人々は、会見での謝罪の言葉を期待していたはずですが、佐野氏が強い言葉で完全否定を行ったことで、ある意味自分に対して反論されたという印象すら持ってしまった可能性があります。
疑惑に対する完全否定が、逆に疑惑を持っている人への挑戦状となってしまったわけです。
参考:「まったくの事実無根」 東京五輪エンブレムのデザイナーが会見、盗用疑惑を強く否定 書体など詳細も説明
このエネルギーが、この記者発表会のあと展開される佐野氏の過去の仕事に対する粗探しを行うエネルギーになってしまった可能性が高い、と考えられます。
同様の構造問題で参考になる事例が、トヨタのプリウスでブレーキ問題が議論を呼んだ2010年2月の記者説明会です。
この際も、記者説明会においてトヨタの経営陣は、専門家に対して問題の技術的背景を説明することに終始しました。それにより専門家は納得したものの、その会見を見た視聴者はトヨタはユーザーに謝罪をしようとしていないと受け止めてしまい、さらに騒動が拡大する結果となってしまっています。
今回の五輪エンブレム会見も、構造は同じです。
本来、この問題は、新国立競技場に続く、組織委員会の不祥事として国民には受け止められていました。
まず、この記者会見でされるべきは、国民に不安を与えていることへの謝罪であるべきで、ドビ氏への対応については真摯に説明して理解を得たいという程度の説明でも良かったかもしれません。
いずれにしても、この会見がきっかけとなり、ネット上では佐野氏の過去の仕事に対する粗探しが本格化する結果となりますから、せっかくの会見の場を逆に敵を増やす場にしてしまったのは実に残念な結果といわざるを得ません。
■メディア対応における逆ギレは致命的
さらに佐野氏側の対応で事態の悪化に輪をかけたのがメディアに対する広報対応です。
様々な情報を伝え聞く限り、会見後の佐野氏側の広報対応はお世辞にも良いとは言えない状況になってしまっていたようです。
佐野氏側からすると、ドビ氏の行動により自分達があのような状況に追い込まれて、自分達が被害者であるという意識が強かったであろうことは容易に想像出来ます。別の仕事におけるトレース問題によって、エンブレムに対しても疑惑が広がってしまった状態で、四面楚歌の状態に陥り、メディアに対しても不信感を持ってしまっていたこともあるでしょう。
ただ、ここまで世間の注目が集まっている中での、メディアに対する逆ギレ対応は完全に致命傷となります。
参考:佐野氏広報担当が「サントリー」問題を謝罪 それ以外の疑惑は「何一つない」
例えば、上記のスポーツ報知の記事では、「徒歩で会場入りした佐野氏は、報道陣のカメラを目にするなり「撮らないでもらえますか」と不機嫌な表情。呼びかけには応じることなく、中へと入った。」や「語気を強めて「1個ミスしたらすべてダメになるんですか? エンブレムの制作過程に何か問題があるのですか?」とまくし立てる場面もあった。」、「佐野氏は終了後も報道陣に対応することはなく、タクシーで会場を後にした。」など、明らかに佐野氏側のメディア対応が強気なものであったことが伺えます。
疑惑の火が消えずに敵に回っている人が増えている状況で、ネットだけでなくマスメディアの記者の方々も敵に回してしまうのは、致命的です。
同様の失敗事例は、雪印集団食中毒事件での当時の雪印社長による「わたしは寝ていないんだよ!!」発言や、集団食中毒を引き起こした「焼肉酒家えびす」の社長による逆ギレ会見が有名です。
参考:逆ギレしたかと思うと涙の土下座 「集団食中毒」社長態度一変の理由
仮にその場でのメディアの取材が行きすぎたものであったとしても、それに対して逆ギレして発言をすると、他のメディアや視聴者も、その逆ギレの矛先が自分であると受け止めてしまい敵に回ることになります。
本来メディアが同情的な状況で、メディアに対して冷静な対応ができていれば、上記の佐野氏広報担当の謝罪記事も全く記事のトーンが変わります。
それが逆ギレにより、メディアの記事があそこまで批判的に書かれてしまうと、これを見た読者も敵に回るという負の連鎖が発生するわけです。
特に佐野氏の事務所におけるトレース問題をスタッフの責任にした上でのこの逆ギレは、政治家が不祥事を秘書の責任にして自分は責任回避をする典型的なパターンという印象を免れません。残念ながら自爆に近い、非常に問題のある対応だったと言えるでしょう。
ネット上での疑惑が消えないからこそ、せめてメディアに対する対応は冷静に行わなければならなかったのですが、この構造によりもはやこの騒動は止められないところまで来てしまっていたと言えます。
■責任者の不在こそが最大の問題
最終的に、今回の五輪エンブレム騒動は、何とか事態を収束したいと考えた組織委員会が再度8月28日に会見を行い、再度技術的な説明を行うことで疑惑の払拭に努めようとしますが、最初の案にも類似のロゴが存在することや、説明時に利用した資料自体に画像の盗用が存在することが指摘されることになり逆に深刻な延焼を引き起こしました。
その結果、最終的に佐野氏側が模倣については完全否定を続けながらも、エンブレムについては白紙撤回をする、という非常に分かりづらい結果となってしまいます。
最初から最後まで、もやもやが続く残念な展開だったと言えるでしょう。
このもやもやが続いている状況という点に、今回の炎上の最大の原因であり最大の問題であるポイントが隠れています。
それが「責任者の不在」です。
先ほど、プリウスのブレーキ問題において、トヨタ側が炎上の火種の背景を見誤った質疑対応を会見でしてしまい炎上が広がった事例をご紹介しましたが、トヨタ側はその後スタンスを変えます。
最終的には豊田章男社長が自ら米国の公聴会で謝罪をし、その後販売店や工場の従業員を集めた会合にも出席、アメリカのテレビ局・CNNに向かい、トーク番組にも生出演するなど、あえて厳しい場にも社長自ら出ることによって積極的に謝罪を行い、世間のムードを大きく変えることに成功しました。
この騒動の豊田章男氏の最終的な対応については多くの方々が賛辞を送っています。
参考:豊田章男の涙:日本人の心を掴む「男泣きの作法」 名経営者のコミュニケーション術
この際にポイントになっているのがリーダーシップのある責任者による誠意ある謝罪です。
そもそも、今回の五輪エンブレム騒動において、騒動に対してリーダーシップを持って対応しなければいけないのは組織委員会であって、エンブレムを応募した佐野氏ではなかったはずです。
新国立競技場の白紙撤回に至る経緯においても、組織委員会や関係者が全ての責任をザハ氏のデザインに押しつけるような議論が目につきましたが、本来は公募を通じて選ばれた新国立競技場やエンブレムのデザインは、組織委員会側が選んだ時点で全ての責任の主語が組織委員会に移っていると考えるのが普通でしょう。
さらに、今回の五輪エンブレム騒動においては、最終的に選ばれていたエンブレムは、佐野氏が応募したデザインが元となり組織委員会との繰り返しのやり取りにおいて完成したものであることが明白になっています。
そういう意味では、実は明らかに今回のエンブレムは佐野氏と組織委員会の共同作業による成果物であり、最初の会見でいかにも佐野氏個人によるデザインであるように説明させた時点から対応を間違ってしまったというのが率直な印象です。
実際には、騒動が発覚したタイミングで、リーダーシップを持った責任者が出てきて、率直に五輪エンブレムについて国民に不信感を持たせるような結果になっていることをお詫びすることが、あの段階で一番必要なことだったと考えられます。
少なくともドビ氏の法的措置が明確になった会見のタイミングで、責任者が登場し、騒動に対するお詫びを誠意を持って国民に対して伝え、ドビ氏の法的措置に対しては委員会側で誠意を持って理解して頂けるように努めたい、と説明していれば、相当印象は違ったはずです。
もしくは、今回の五輪エンブレムを選んだ思いや、エンブレムも含めたオリンピック全体に対する熱意を説明することで、ベルギーのロゴに結果的に似てしまったことをお詫びしつつ、是非このエンブレムで本大会を迎えたいから支援して欲しいと誠意を持ってお願いすることで、世論にドビ氏ではなく日本側、組織委員会側の味方になってもらうという選択肢もあったはずです。
そうした責任者の誠意ある説明や、騒動自体に対する謝罪によって事態が沈静化すれば、実は佐野氏個人の仕事に対しての粗探しが始まることもなかったかもしれませんし、佐野氏がメディアに対して逆ギレすることもなかったかもしれませんし、佐野氏の内部資料を基にした弁明会見を行うことでさらなる画像転用の問題が注目されることも、そもそもなかったかもしれません。
そうすれば、ここまで私たちが楽しみにすべき2020年のオリンピックに対して複雑な気持ちになることもなかったかもしれないわけです。
■五輪エンブレム騒動を良いきっかけにするために
もちろん、五輪組織委員会のようなプロジェクトチーム的な組織は、様々な場所から集まった人々で組織されている委員会でしょうし、通常の企業のように明確にリーダーシップを持った方が統率している組織ではないのかもしれません。
ドビ氏が法的措置をちらつかせた段階で、IOCも巻き込まれてしまい、組織委員会だけでは対応出来ない問題になってしまったという事実も悪い方向に影響してしまっているとも聞きますから、組織委員会の方々だけの権限では対応が難しかった問題なのかもしれません。
そもそも、佐野氏の仕事における管理体制自体に対するプロの方々からの問題提起も聞こえますから、佐野氏が選ばれた時点で、組織委員会としてはどうしようもなかったという見方もあるかもしれません。
また、こうした議論は全て後から振り返った「たられば」の話であって、今更しても仕方がない話なのは明白です。
ただ、今回の五輪エンブレム騒動の真に恐ろしいのは、まだ最初の案の白紙撤回がされただけであって、新国立競技場同様ゴールが全く見えていないという点です。
組織委員会の対応が、今後も同様に責任者不在のように見える対応を続けた場合、広くエンブレムを公募で集めようがプロセスをオープン化しようが、第二の五輪エンブレム騒動がおこった際に、同様の対応をしてしまうと、また同じネガティブスパイラルに入ってしまう可能性が否定出来ません。
今、組織委員会の方々に是非行っておいていただきたいのは、何故ここまで技術的には問題が無かったはずの五輪エンブレム騒動が、オリンピックの歴史に残る汚点になりかねない騒動になってしまったのか、という振り返りと総括だと思います。
逆に言えば、今回の騒動をきっかけに、オリンピックに批判的な方々とのコミュニケーションのあり方を認識し、オリンピック招致の際に実現出来たはずの日本全体を巻き込んで盛り上げていくようなコミュニケーションのスタイルを再度確立することができれば、オリンピック開催の折には今回の騒動が良いきっかけになったと振り返ることも可能だと感じます。
また、まさにそのために「東京2020エンブレム委員会」に様々な方々が参加され議論を尽くされていることを期待しています。
2020年に見せてもらえるだろう感動を、私たちが素直な気持ちで心から感動として受け止めることができるように、是非組織委員会やオリンピック関係者の方々には、今回の騒動をなんとか参考にしてこれ以上の同様の騒動の再発を防いで頂きたいと思いますし。
開催前の騒動すら忘れさられてしまうぐらい、素晴らしい感動だけが記憶に残る東京オリンピックが開催されるために、がんばって頂きたいと、心から祈る今日この頃です。