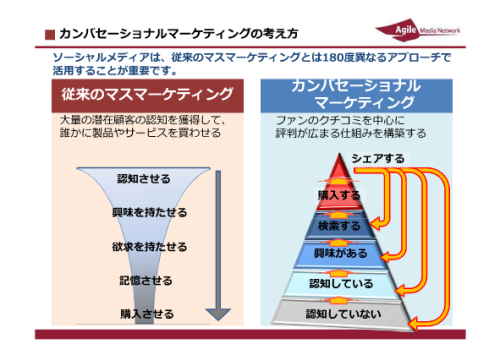「逆パノプティコン社会の到来」は、副題に「ウィキリークスからフェイスブック革命まで」とあるように、ウィキリークスやフェイスブックのような新しいメディアや組織が、世界をどのように変えようとしているか考察している書籍です。
「逆パノプティコン社会の到来」は、副題に「ウィキリークスからフェイスブック革命まで」とあるように、ウィキリークスやフェイスブックのような新しいメディアや組織が、世界をどのように変えようとしているか考察している書籍です。
著者のキムさんから献本を頂いたので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。
この本ではメディア学者であるキムさんならではの俯瞰的な視点から、ウィキリークスやフェイスブック、そして最近プレイステーションネットワークをダウンさせて話題になったハッカー集団「アノニマス」などが、どのように成長を遂げてきたのかを学ぶことができます。
Collateral Murder Wikileaks 投稿者 wikileaks
特に驚くのが、昨年非常に話題になった上記の「Collateral Murder」というビデオから、チュニジアのジャスミン革命、エジプトの革命など、ここ1年間に世界で話題になった出来事のほとんどのに、ウィキリークスやアノニマス、フェイスブックが網の目のように関係していたという事実。
正直、自分がいかに表面的にしかニュースを見ていなかったか。
今回の革命や騒動が、実は様々な面でソーシャルメディア時代ならではの出来事であるかというのを、この本を読むと痛感させられます。
ウィキリークスを巡る騒動やアノニマスによる企業への攻撃自体は、テレビのニュースで見る限り、ウィキリークスやアノニマスというメディアや組織によって引き起こされた良くある内輪もめやトラブルにみえてしまうかもしれませんが、実際には国家と個人のパワーバランス、既存の秩序と新しい勢力とのハレーションとでも言うべき出来事と見るべきなのかも知れません。
フェイスブックなどのソーシャルメディアによって引き起こされる根源的な国家や企業の変化について考えたい方には、非常に参考になる点が多々ある本だと思います。
【読書メモ】
■パノプティコン(全展望監視システム)
監獄の真ん中に看守等が立つ。そしてその看守塔を囲む形で円形の独房があり、そこに囚人を収監する。
■ウィキリークスのミッション
情報の完全透明化を通じて社会における不正を暴くことで、社会をより正義あるものにする
■ウィキリークスの特徴
・完全匿名性の保証
・法的リスクの削減
・多数のミラーサイトの存在
・既存の報道機関との緊密な連携
続きを読む 逆パノプティコン社会の到来 (ジョン・キム) を読むと、ウィキリークスやフェイスブック、アノニマスと言った新しいメディアや組織が世界をどのように変えようとしているのか見えてくるはず。