asahi.com: 経産省部長ブログ「炎上」 PSE法巡り書き込み殺到 – 社会を読んで。
御手洗さんのブログ経由で知ったのですが、PSE法の関連で経済産業省の谷部長のブログが「炎上」して、閉鎖に追い込まれていたそうです。
御手洗さんもブログで「行政に携わる方と非常に近い対話の機会が増えることは、住民のニーズに近い行政サービスを実現する上で、非常に価値のあることでしょう」と書いていますが、国の省庁の生に近い意見を聞けるブログがあるなんて実に画期的なことだったと思います。
私個人はPSE法について無知なので、法律自体の是非は分かりませんし、谷部長がどういう人だったのかは良く分かりませんが、それにしても対話をしようと努力をしてくれる窓口があったのに、そういうブログが存在したのに、その窓口が炎上して閉鎖に追い込まれてしまうというのは実に悲しいことです。
こういうことがあればあるほど、「結局ネットとかブログなんか使って国民の意見を集めても意味ないよね」と官僚の人たちに思われてしまうわけで。
結局、国民の意見なんて聞く必要はないという話に帰結してしまいそうなのが個人的には非常に残念です。
特に個人的に引っ掛かったのが「ブログ更新が平日の勤務時間内だったため「公務中の更新は問題」と議論は思わぬ方向に飛び火した」という部分。
もし、これが電話による苦情を対応という話であれば、苦情郵便に対する返事を書いているという話しであれば、抗議者が庁舎に押しかけてきたのを対応という話であれば。
勤務時間内の対応に、こんな指摘が出るでしょうか?
PSE問題に関わる谷部長のブログ更新というのは、行為としては不特定多数の人たちに経産省の施策への理解を求める、まさに電話対応や対面対応と同じ説明行為だったはずなのに。
人々の非難の矢面にたった行為が褒めらるべきぐらいのところを、「国家公務員法の職務専念義務違反」なんて懲罰をもらうなんて悲しすぎますよね。
しょせん今の官庁におけるブログの位置づけなんてこんなもんなんだというのが良く分かる一文ですが。
今回、谷部長のブログを炎上させてしまった人々は、聞く耳をもってくれたかもしれない谷部長を攻撃して、その後ろにいる手を汚してない人たちに谷部長を後ろから刺させた上、象牙の塔に閉じこもる言い訳を与えてしまったかもしれないわけで。
何とも、いろんなことを考えさせられる出来事です。
ちなみに、御手洗さんも書いていますが、「炎上」という言葉が一人歩きすると、いかにもネットならではの特殊な出来事のように見えてしまうのを個人的には非常に懸念しています。
今回のPSE法問題にしても、結局ブログの「炎上」というのは、人々の間でPSE法に対する疑念や不満が渦を巻いているから、リアクションの出やすいブログやネットが「炎上」という形で盛り上がるわけで。
これまでは人々の声が見えにくかったから「炎上」という分かりやすい現象が出なかっただけだと思います。(それが本当にたまりにたまるとデモとかストライキのような実力行使になるんだと思いますが)
官僚の皆さんには、是非ネットのボヤで済んでるうちに、本質的な問題を踏まえた議論をしていただきたいと切に願います。
スカイプのテレビ電話なら無料で遠隔監視システムができる?
ONEDARI BOYSの企画で、スカイプのまゆさんになんとウェブカムとヘッドセットを頂いてしまいました。
個人的には、以前にもテレビ電話が普及するのは時間がかかるんじゃないかという趣旨の記事を書いたこともあるので、何でウェブカムなんかおねだりするんだと起こられてしまう立場なんですが。
実は、ちょっと試してみたかったことがあります。
それがスカイプのテレビ電話を使った遠隔監視システムです。
ということで早速、試してみました。
遠隔監視システムと言っても、もちろんスカイプを使うので、おおげさなものは必要ありません。
必要なのは、ウェブカムとスカイプだけ。
手順も簡単です。
1.自宅のパソコンにスカイプをインストールしてウェブカムを設置します
2.自宅のパソコンのスカイプの設定メニューから「詳細」の中で「自動応答」という項目にチェックをつけます。
以上、終了です。
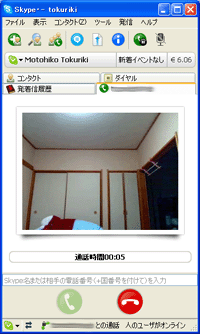 あとは、会社のPCから自宅のPCにビデオコールをするだけ。
あとは、会社のPCから自宅のPCにビデオコールをするだけ。
コンタクト欄の自宅のPCのビデオマークをどきどきしながらクリックすると・・・
おお、出ました!
我が家の映像です!
と言っても、今は家の中でやっているので出来て当たり前なんですが(汗)
会社からできるかどうかは月曜日にやってみることにします。
それにしても、カメラさえあれば無料で遠隔監視システムまで、できてしまうんですから凄いですねー。
せっかくウェブカムを買ったものの、テレビ電話をする相手がいなくて結局無駄になっているという方は、是非スカイプで遠隔監視システム構築を試してみてはいかがでしょうか。
家族やペットの安否確認や電源の切り忘れの確認、浮気防止など、様々な可能性が広がること間違いありません。
ただ、誰からかかってきてもビデオが自動応答するのは問題なので、あまり応用は利きません、あしからず。
もう少しマジメなテレビ電話のレポートを読みたいという方はこちらをどうぞ。
・スカイプ! スカイプ! スカイプ! テレビ電話!
・skypeだ!スカイプだ!テレビ電話だ!デジカメだ!
・スカイプとUSBカメラとヘッドセット
日経WOMANに取材してもらいました。
 日経WOMAN4月号の「そろそろ、わたしもブログデビュー」特集に、アルファブロガーについてインタビューしていただいた記事が掲載されました。
日経WOMAN4月号の「そろそろ、わたしもブログデビュー」特集に、アルファブロガーについてインタビューしていただいた記事が掲載されました。
(mさん、tさん、ありがとうございました。)
日経WOMANでブログというとちょっとぴんと来ないかもしれませんが、齋藤朱保さん、増田真樹さん、和田亜希子さん、渡辺英輝さん、R30さんと、錚々たるメンバーにインタビューを敢行して分かりやすくまとめられていますので、現在のブログをめぐる状況を10ページでさらっと読みたい人には男女を問わずお勧めです。
それにしても、やっぱり女性誌の表紙はお洒落ですね・・・
(自分のブログじゃないみたい)
月刊 旬なテーマに取材してもらいました。
 中経出版の「月刊 旬なテーマ」2006年4月号に、アルファブロガーについてインタビューしていただいた記事が掲載されました。
中経出版の「月刊 旬なテーマ」2006年4月号に、アルファブロガーについてインタビューしていただいた記事が掲載されました。
インタビューしていただいたKさん、ありがとうございました。
読者の少ないブログの方が価値があるかもしれない
先日、「ブログを多くの人に読んでもらえる方が良いとは限らない」という記事を書いたが、1月にそれに関連してちょっとショックな出来事があった。
ブロガーカンファレンスの打上のときに、小鳥さんに「徳力さんはアルファブロガー投票企画とかやってますけど、僕らみたいなブロガーはどういう位置づけなんですか?」と聞かれてしまったのだ。
どうも、投票企画を率先的にやってたために、「徳力は人気ブログ至上主義者」だと思われてしまっていた模様。(きっと多くの人がそう思っているんだろうけど、正直、結構悲しかった)
この場を借りて、改めて釈明させていただくと、実は個人的には人気ブログ自体にはそれほど興味はなかったりする。
こんな書き方をすると、逆に人気ブログに選ばれた方々に失礼かもしれないが、そもそもアルファブロガー投票企画を実施したのは、いわゆる人気ブログランキングとかアクセス数ランキングの視点だと、芸能人ブログとか、鬼嫁日記のような面白い読み物系のブログに注目が集まってしまうので、そうじゃないビジネス系のブログで多くの人に読まれているのは誰か知りたかったから。
で、アルファブロガーとの座談会とかインタビュー本とかを企画したのは、もっと多くの日本のビジネスパーソンが、こういうブログを書くようになったらブログも、もっと日本も面白くなるんじゃないか、と思っていたからだ。
その辺の感覚は、梅田さんのBlog論がらみの記事で「大組織に属する超一流の技術者や経営者が本気でBlogを書くということも、どうも日本では起こりそうもない。」という問題提起がされていたのをご存知の方であれば、理解していただけるのではないかと思う。
だから、当然個人的には、アルファブロガーに選ばれるようなブログがもっともっと増えて欲しいと思っている。
ただ、今からブログを始めて、すぐに有名ブログになることは不可能だとは言わないが、相当難しいと思う。
既に各分野ごとにある程度有名ブログの中心というのはできているし、これだけブログが増えてくると自分のブログに気づいてもらうのも一苦労だ。
なので、最初はアクセス数や広告収入を増やすことを目的にブログを始めない方が良いんじゃないか、と口説く書いているわけだ。
じゃあ、ブログを書くのは自分のためにしか役立たないかというと、もちろんそんなことはない。
仮に多くの人に読まれることが無かったとしても、それでも、多くのアルファブロガーのようなビジネス系、論考系のブログを書くことは、かならず自分のためだけでなく、他の人の役にも立つと思う。
その点で、個人的に大きな影響を受けたのが、昨年ダン・ギルモアさんが来日した際にイベントで発言されていたこと
たとえば、15人の読者しかいないブログでも、その人たちにとってものすごく切実で、非常に熱心に読まれているとすれば、人気があって(読者の数が多い)ブログよりも、情報の価値が高いと思う。(当日の詳細は小林恭子さんのブログをご覧下さい)
ブログを既存のマスメディアと同じ価値感で捉えてしまうと、アクセス数や購読者数が多いこと=良いことと、考えてしまいがちだ。
でも、インターネットやブログによって、既存のメディアではカバーしきれなかった膨大な情報が、私たち一般人によって発信可能になったことが、実は一番面白いところだと思う。
実際、最近ブログを読んでいるおかげで、ニュースサイトでは取り上げられないけれども自分のビジネスにとっては重要なニュースに気づくことが出来たり、検索した結果、ニッチなサービスに関する他の利用者の感想なんかを読むことが出来るようになった実感がある。
実際、アルファブロガー本企画でインタビューをした際にも、それぞれのアルファブロガーの方は、皆さん自分のためや趣味でブログを書いていたのが、いつのまにか多くの人に読まれるようになったという話をされていたのが印象的でした。
そういう意味では、アクセス数や読者数を気にしながらブログを書くぐらいなら、多くの人は気にも止めないようなニッチで深い自分が興味のある話題を、自分なりの自然体の文章でブログに綴っているほうが、本当の意味で価値が出せるのかもしれない。
そんなことを思ったりするわけです。
(そうは言ってもやっぱり読者数とか、アクセス数は気になるんですけどね)
「へんな会社」のつくり方 (近藤 淳也)
 次世代の経営者として注目されるはてなの近藤さんの本。
次世代の経営者として注目されるはてなの近藤さんの本。
翔泳社さんから献本を頂きましたので、遅ればせながらメモを書いておきます。
書籍の内容自体は、CNETに連載されていたブログをベースとしているので、一度読んだ内容も多いのですが、あらためてまとめて読むと考えさせられるところが多々あります。
特に参考になるのは、すべてのことに対して「それは本当か?」と常識を疑って考えているところ。
最後の方にアインシュタインの「常識とは18歳までに身につけた偏見のコレクションのことをいう」という言葉が紹介されていますが、そう言われてみれば結局企業経営論なんてここ100年程度の歴史しかないわけで。
過去の歴史の中で常識となってきたことに対して常に疑問を持ち、自らの会社にあった仕組みを模索し続ける姿には頭が下がります。
「へんな会社の作り方」というタイトルにはなっていますが、実際にこの本の中で近藤さんがメッセージとして発しているのは、実はインターネット時代においては既存の会社の方が「へんな会社」なんじゃないの?ということかもしれません。