 「媚びない人生」は、「逆パノプティコン社会の到来」などの書籍で知られるジョン・キムさんが書かれた書籍です。
「媚びない人生」は、「逆パノプティコン社会の到来」などの書籍で知られるジョン・キムさんが書かれた書籍です。
献本を頂いていたので、遅ればせながら書評抜き読書メモを公開させて頂きます。
タイトルからして非常にインパクトのある本ですが、キムさんの視点ならではのこれからの日本社会を生き抜くためのメッセージが詰まっていますので、これから就職を考えている大学生や、壁にぶつかって悩んでいる社会人の方には参考になる点がある本だと思います。
【読書メモ】
■社会に革命を起こすことは難しく、時間がかかるものだ。しかし、内面の革命は今この瞬間にスタートできる。
内面とは「感情」「思考」「言葉」「行動」の4つで構成される
■大学を卒業すると状況は一変する。
社会人になった途端、社会は大学とはまったく異なるゲームのルールの下で運用されていることに段々と気づくようになる。大学では、権威は適当に避けて通ればよかった。お金を払う立場だからだ。しかし、会社に入るとお金をもらう立場になる。
投稿者: 徳力 基彦
mixiのプライベートグラフ戦略が正しかったということが、LINEによって証明されたという仮説
先週末に、トライバルメディアハウスの社員の方が書いたブログが話題になり、最終的に社長の池田さん名で謝罪文まで出す結果になるという騒動がありました。
・社員の「mixiは死ぬ」ブログに謝罪 SNSマーケティングのトライバルメディア
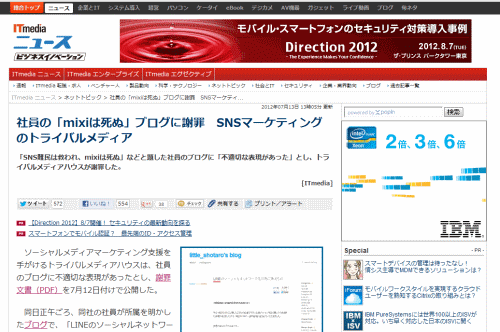
上記の件では、記事タイトルや記事内で「mixiは死ぬ」という表現を使ってしまったということで、お詫びすることになったようですが。
実はこれでプレスリリース謝罪文の発行が必要になるなら、私自身も先日ツイッター上で「LINEすごいなぁ。完全にFacebookをぶち抜きましたね。mixiはLINEにとどめを刺される形になるとはなぁ。」というような類似の発言をしていますので、実は他人事ではありません。
実際に、この発言を見て言葉の使い方が不適切と思われた方も少なくないようなので、訂正も兼ねてブログに発言の背景の詳細説明を書いておきたいと思います。
まず、情報開示として、私の知り合いの方なら良くご存じだと思いますが、私はmixiには多数の知り合いや友人がmixiにいますし、mixi社長の笠原さんは尊敬している経営者の一人で、主催したイベントであるWISHに笠原さんにビデオ出演してもらったり、取締役の原田さんにパネリストで来てもらったりしている人間です。
2010年には、TechCrunchの下記のような記事でmixiにエールを送ったこともあります。
・mixiは、mixi日記成功の呪縛から解き放たれることはできるか。
ブログを書き始めた2004年頃のmixiやGREEによる第一次SNSブームが私の人生を大きく変えたのは間違いありませんし、それから8年以上mixiの動向はウォッチし続けてきました。
そういう意味では、私個人はmixiに盛り上がって欲しいと思っている人間ですし、企業のソーシャルメディア活用を支援する立場の人間としても、国産SNSの代表であるmixiの存在が、海外のプレイヤーとの差別化を図る上でも非常に重要になる立場にあるのが正直なところでもあります。
企業向けのmixiページ勉強会を主催したり、企業のmixiページ開設の支援も行っていますから、実際には、上記のような発言をすべきではない立場の人間だと言えるでしょう。
ただ、だからといって私がブログやツイッターで中途半端にmixiを持ち上げたところで逆にステマ呼ばわりされるのがオチですし、そんなもの誰もこのブログに求めていないと思いますので、あえて発言の背景を正確に書きたいと思います。
それはLINEの登場によって、mixiのプライベートグラフ戦略が見直しを迫られる可能性がでてきたと感じたということです。
もちろん、戦略の結果は後になってみないと分かりませんし、当然mixiが挽回できる可能性もあるわけですから、「とどめを刺される形」という表現は強すぎたと思います。
とはいえ、今更言葉を繕っても仕方が無いですし、mixiにいる友人や知り合いの方々を鼓舞する意味であえて書きます。
現在のmixiはFacebookを仮想敵として意識しすぎた結果、LINEとFacebookの両者に板挟みになってしまってきていると思います。
リーン・スタートアップ(エリック・リース)は、今後10年は新規事業やスタートアップのバイブルとして読み継がれていく本になると思います。
 「リーン・スタートアップ」は、スタートアップの成功のためのポイントについて、エリック・リース氏が考察されている書籍です。
「リーン・スタートアップ」は、スタートアップの成功のためのポイントについて、エリック・リース氏が考察されている書籍です。
献本を頂いていたので、遅ればせながら書評抜き読書メモを公開させて頂きます。
いまやシリコンバレーやスタートアップ業界において、「リーン・スタートアップ」という言葉は標準語に近い状態になっていると言えます。
日本にも著者が出版記念で来日して、ワールドビジネスサテライトで取り上げられるなど話題になりましたが、海外のスタートアップ系のイベントに出ると必ずと行って良いほど、このキーワードを耳にすることになるといっても過言ではないでしょう。
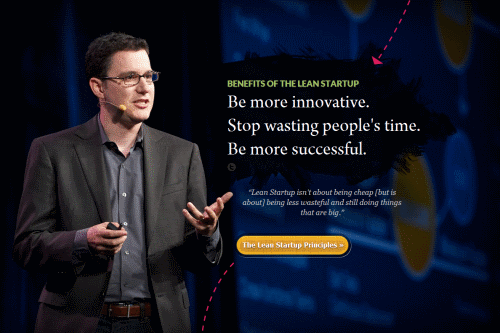
実際、本を読んで個人的にも驚いたのは、これまでに様々なところで議論されていたスタートアップが抱える課題やその乗り越え方が、実に体系的に整理されていること。
同じような話を語っている人は、これまでにもたくさんいたと思いますが、ここまでそのポイントを整理して一冊にまとめた本はなかったと思います。
ピボットやMVP(minimul viable product)など、スタートアップ系のイベントで登壇者が解説なしに使うようになっている言葉のコンセプトも説明されていますから、まさに今後しばらくはスタートアップ業界のバイブルとして使われるようになる本だと言えると思います。
ちなみに、個人的にちょっと嬉しかったのは、リーン・スタートアップのリーンという言葉が、トヨタのリーン生産方式から来ていることが何度も明確に書かれていること。
書籍の中でも「第二次世界大戦後、トヨタをはじめとする日本の自動車メーカーは最新の大量生産技術を駆使する米国の巨大向上に太刀打ちできなかった。この状況を逆手にとり、バッチサイズの縮小で成功したのが大野耐一や新郷重夫らのイノベーターだ。」と、リーン生産方式を開発した大野耐一氏、新郷重夫氏の功績をたたえていますが、現在のネット産業における日本のスタートアップの生きる道が、一つここに描かれているように思います。
GoogleやFacebookのような巨大なインフラになりつつある米国のウェブサービスに対し、日本のスタートアップはどのように自らの役割を定義していくべきか。
そんなことも妄想したくなる本です。
スタートアップに携わっている人はもちろん、変化の激しいインターネットやソーシャルメディアに携わっている方には是非読んで欲しい本です。
【参考記事】
・「リーンスタートアップ」著者エリック・リース氏が来日講演。”スタートアップとはマネジメントのことだ” - Publickey
【読書メモ】
■リーン・スタートアップの5原則
・アントレプレナーはあらゆるところにいる
・起業とはマネジメントである
・検証による学び
・構築-計画-学習
・革新会計
■リーン・スタートアップという名前は、トヨタで大野耐一と新郷重夫が開発したリーン生産方式にちなんだものだ。リーンな考え方は、サプライチェーンや製造設備の運営方法を根本から変えつつある。
■スタートアップの三層構造
・ビジョン
・戦略(ピボット)
・製品(最適化)
続きを読む リーン・スタートアップ(エリック・リース)は、今後10年は新規事業やスタートアップのバイブルとして読み継がれていく本になると思います。
ストーリーとしての競争戦略(楠木建)を読むと、従来の経営戦略本を読んだだけでは問題が解決しなかった理由が見えてくると思います。
 「ストーリーとしての競争戦略」は、楠木建さんが競争戦略について考察された書籍です。
「ストーリーとしての競争戦略」は、楠木建さんが競争戦略について考察された書籍です。
昨年非常に話題になっていたので買って読んでみていたのですが、遅ればせながら書評抜き読書メモを公開させて頂きます。
通常、経営本や戦略本というと個人的には海外の著者の本しか買いません。
日本においてはどうしても書籍の出版のサイクルが早すぎるために、中身の濃いビジネス本が少なく、読みやすいノウハウ本が中心になっている印象が強いからです。
おそらく海外においては英語と言うこともあり、しっかりと書いた分厚い経営本や戦略本が比較的寿命が長く売れ続けるのだと思いますが、日本においてはそういうポジションを取るのが難しいというのも影響しているのでしょう。
ところが、この「ストーリーとしての競争戦略」は、実に本格的な戦略本です。
正直、日本でこれほど本格的に体系立って書かれる経営本が書ける方がおられるとは思っていませんでした。
海外の戦略本と並べても遜色ない、楠木さん独自の競争戦略論と言えると思います。
一回読んだだけで全てが理解できるとはとても言えず、何度も繰り返し読みたくなる本だと思います。
まだ読んでいない方は、是非読んでみることをお勧めします。
「イノベーションのジレンマ」や「ブルー・オーシャン戦略」とあわせて読むのもお勧めです。
【読書メモ】
■静止画を動画に
従来の戦略論には「動画」の視点が希薄でした。戦略のあるべき姿が動画であるにもかかわらず、その論理を捉えるはずの戦略「論」はやたらと静止画的な話に変更していたように思います。
■なぜユーザーは静止画的な短い話を好むのでしょうか
・とにかく忙しい
・主たるユーザーが、経営者と言うよりも経営企画部門などの「戦略スタッフ」であることが多い
・「プロフェッショナル経営者」という幻想。経営者の戦略スタッフ化
・コンサルタントによるマーケティングの影響
・静止画的な短い話は、コミュニケーションが簡単
・マクロな経営環境の変化は、とりわけ長い話を嫌がる傾向を加速させている
続きを読む ストーリーとしての競争戦略(楠木建)を読むと、従来の経営戦略本を読んだだけでは問題が解決しなかった理由が見えてくると思います。
今日の深夜0時15分から、NOTTVのソーシャル@トーク #エンダン に出演させて頂くんですが、ライブで質問とか受け付けるようなので、お手すきの方は是非助けて下さい。
タイトルで言いたいことは、ほぼ言い切ってしまいましたが本日の深夜0時15分からNOTTVのソーシャル@トーク #エンダンという番組に出演させて頂くことになりました。

NOTTVは、4月にはじまったスマートフォン専用放送局なんですが、この番組はUstreamでも配信されてるライブ番組です。
メールで依頼を頂いた時は、昔懐かしいBlogTV的なネット側にフォーカスした番組なのかなとか思って気軽に受けてしまったのですが。
どうも出演者一覧を見る限り、通常は芸能人の方が出演する番組のようなので、完全に私の写真が並んでることに違和感ありまくりです。

芸能人の方と長時間からむのって、広瀬香美さんのUstream番組に出た時ぐらいしか無くって、かなり不安。
おまけに番組前や番組中に視聴者からライブでコメントを受け付けたりとかもしてるみたいなんですが、どう考えても私のことなんかNOTTVの通常の視聴者の方は知らないでしょうから、ほとんど全く反応が無いだろうというのを今から超心配しております。
多分、私のツイッターのフォロワー数が多いからと言うので出演依頼出して頂いたんだと思うんですけど、私のフォロワー数が多いのは、ツイッターのおすすめユーザーに入れて頂いてるからなので、こういうライブ系で大勢返事くれるとか無いんですよね・・・
そんなこんなで、これで私の回があまりに無風で、ツイッター盛り上がってないよね、とか番組の関係者の方々に勘違いされるのも申し訳ないので、もし、今日の深夜に家でパソコン開く余裕があるよ、という方はUstream放送の方からでも助けて頂けるとありがたいです(涙)
番組のハッシュタグは #エンダン みたいですので、Ustreamが見れない方はそちらでもどうぞ。
スタートアップのタイムマシン経営は、インドネシアのような東南アジアではまだまだ機能するかもしれない
 スタートアップのニュースサイトである「Startup Dating」に不定期で記事を投稿させて頂いています。
スタートアップのニュースサイトである「Startup Dating」に不定期で記事を投稿させて頂いています。
こちらのブログとStartup Datingに同じ記事をダブルポストする形になりますので、お好きな方でご覧下さい。
先日投稿したStartup Datingの記事はこちらです。
--------------------------------ーーーーーーーーーーーーー
もう2週間前の話になりますが、ジャカルタで開催されたStartup Asia Jakartaに参加してきました。ファーストインプレッションは「海外市場での成功には、ネットの世界でもきめ細かいローカライズが重要」という記事に書きましたが、2日間を追えての感想をまとめておきたいと思います。

まず率直な印象は「すごい盛り上がってるなぁ」の一言につきます。もちろん、日本も最近は様々なインキュベーターや、スタートアップ支援の仕組みができてスタートアップバブルの様相を呈している印象もあり、「なぜスゴそうな人も大ゴケするのか? テーマで間違うスタートアップ」なんて記事も話題になっていましたが、ジャカルタで感じた印象はそれよりももっと根源的な盛り上がり。
何しろインドネシアは現在インターネット利用者の伸び率が世界トップ3に入るほどの勢いらしく、その成長ぶりは東南アジアでも群を抜いています。おまけに何しろ人口も非常に多い国ですから、今後経済が発展すればネット人口やネット産業が発展するのは自明の理。シンプルにいわゆる「タイムマシン経営」の手法で、米国や日本では流行ってるけど、まだインドネシアで流行っていないサービスを今のうちに始めておけば、十分それが今後ブレイクする可能性があるわけです。まさに日本のビットバレー頃の雰囲気とかって、こんな感じだったのかなぁと思わせるイベントでした。
ただ、初期の米国のネットバブルは、まだ一部では盛り上がりつつも本当にインターネットが社会を変えるのか多くの人は半信半疑、という状況だったと思いますが、インドネシアにおけるそれは確実に来る未来は分かっているので、誰がそれをつかむのか、という少し趣の違う競争のように感じます。