mixi売却のニュースが流れて騒がしい傍ら、やまもといちろうブログ方面から私宛のスルーパスが送られていたようなので、取り急ぎ反応。
・イケダハヤト的なるもの: やまもといちろうBLOG(ブログ)
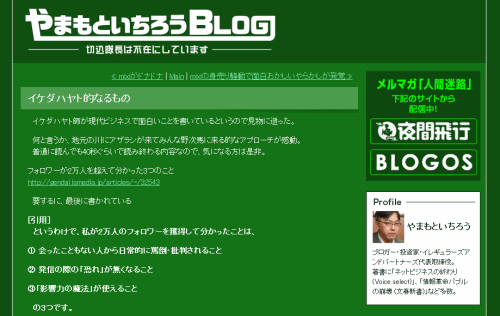
簡単にまとめるとイケダハヤトさんが、フォロワー2万人超えると下記の三つのことが起こる、と書いていたのに反応された模様。
① 会ったこともない人から日常的に罵倒・批判されること
② 発信の際の「恐れ」が無くなること
③「影響力の魔法」が使えること
いつのまにか、イケダハヤトさんは切込隊長のウォッチ対象にもなったんだー、というのが感慨深いなぁという話は置いておいて。
とりあえずフォロワー数激減のくだりは、そもそもおすすめユーザーに載せてもらって自動的に22万まで行ったのが、制度がなくなって安定して減少しているだけ。
毎週毎週フォロワー数が減っているのを確認するのが辛いだけで、ツイッターの利用環境には特に何も変化はありません。
で、これだけだとつまらないので、上記の話についでに乗っかりたいと思います。
ちなみに、丁度ネタフルでコグレさんがスタンスをまとめられているんですが、三つのポイントについての基本的な感想は同じです。
・[N] ツイッターでフォロワーが増えると批判・罵倒されるのか?
実際、オンライン上で知名度が上がったり、読者が増えたりすることにより、批判する人が増える現象というのは、実はブログ時代から良く言われている話。
個人的に記憶に新しいのは梅田望夫さんが2005年にブログで「500-3,000PV/日あたりが、Blogを書いていて、けっこう楽しいいいゾーンなんじゃないかな、と思ったりする。そのくらいだと、読みたいと意図して訪ねてくれる人がほとんどで、それ以上になると、背景を知らずに何かの拍子に飛び込んでくる感じの人が増えてくる。」という話を書かれていたこと。
要はページビューが少ないブログの時は、ブログの書き手のことを知っている人や面識がある人が読者の中心なので、何を書いてもそんなに批判されることはあまりないんですが、PVが増えてくると他のブログ経由などで様々な書き手の背景を知らない人がブログに訪れるようになるので、当然趣旨が伝わらなかったり、批判されることも増える、という話。
投稿者: 徳力 基彦
PULLの哲学(ジョン・ヘーゲル3世)を読むと、ソーシャルメディアを上手く使うためには、プッシュではなくプルの精神が重要なことが分かります。
 「PULLの哲学」は、インターネットの普及によりおこっている考え方のパラダイムシフトについて考察された書籍です。
「PULLの哲学」は、インターネットの普及によりおこっている考え方のパラダイムシフトについて考察された書籍です。
個人的にもソーシャルメディアにおけるプルの重要性を自己流でアピールしていた人間なので、タイトルが気になって買って読んでみていたのですが、遅ればせながら書評抜き読書メモを公開させて頂きます。
この本では、インフラの変化、知識のフローの波、組織の革新という三つのパラダイムシフトにより、いろいろなものの価値観がプッシュからプルへと大きく変化していると考察されています。
実際問題、ソーシャルメディアの使い方が上手い人というのは、短期的にメッセージをプッシュすることによって短期的な利益を獲得しようとするのではなく、長い目で見て自分のところにほかの人たちを引き寄せてくる中長期的な投資と考えている人、というのが個人的なイメージだったため、この書籍で描かれているプッシュとプルの違いというのは非常に腹に落ちました。
どうしても従来の組織や仕事のやり方の価値観から、上手くソーシャルメディアを活用できないという方には、お勧めしたい一冊です。
【読書メモ】
■プルの力とは、チャンスが訪れたときや困ったときに、必要な人材やリソースを自分のところに引き寄せる能力のことを言う
■プッシュの力は、まずニーズを予測することから始まる。そして次に、予測したニーズに必要な人材とリソースが、正しいタイミングで手に入るようにに準備をする。
■弱い絆とは、相手のことをほとんど知らないような弱いつながりだ。それでも、そのつながりを介して、全く縁のなかったようないわゆる「濃い」世界に参加することができる。
■プッシュからプルへの大きなシフトの三つの波
・第一の波:インフラストラクチャーの変化
・第二の波:知識のフロー
(知識のストックよりも、新しい知識のフローの方が大切に)
・第三の波:組織の革新
続きを読む PULLの哲学(ジョン・ヘーゲル3世)を読むと、ソーシャルメディアを上手く使うためには、プッシュではなくプルの精神が重要なことが分かります。
必ず結果が出るブログ運営テクニック100(コグレマサト、するぷ)を読むと、ソーシャルメディア時代だからこそブログを再評価すべき理由が良くわかると思います。
 「必ず結果が出るブログ運営テクニック100」は、「クチコミの技術」や「マキコミの技術」の共著でお馴染みのコグレさんと、和洋風のするぷさんが書かれた書籍です。
「必ず結果が出るブログ運営テクニック100」は、「クチコミの技術」や「マキコミの技術」の共著でお馴染みのコグレさんと、和洋風のするぷさんが書かれた書籍です。
献本を頂いたので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。
この書籍は、副題に「プロ・ブロガーが教える”俺メディア”の極意」と書かれているように、日本ではまだまだ数少ない「プロブロガー」であるコグレさんとするぷさんが、二人のテクニックやコンセプトを赤裸々にまとめている本といえます。
日本における2003年以降のブログブームの過程で、様々なブログ本が出版されてきましたから、今このタイミングでブログ本が出版されることを、いまさらなんで?と思われる方も多いかもしれませんが、実はソーシャルメディアがなかったころのブログの書き方と、ツイッターやFacebookのようなソーシャルメディアが普及してからのブログの書き方というのはかなり変化があります。
昔は何しろブログを購読してもらうためにはブラウザのブックマークに登録してもらって毎日訪問してもらう習慣をつけるとか、RSSリーダーのような特殊なツールを使ってもらわないとなかなか読者は増えなかったのが実態。結果的にSEOにより検索経由のアクセスに主な読者獲得手段を頼っているブログが多かったと思います。
それがツイッターやFacebookのようなフィードの仕組みにより、たまに各ブログの記事を友達や知り合いに読んでもらうことは非常に容易になりました。
そういう意味では、この本で「ブログがWebでのホームになる」と書かれているように、ブログをストックの場所と割り切り、ツイッターやFacebookと組み合わせていくという視点は非常に重要だと思います。
この本ではソーシャルメディア普及前後の両方の時代を知っている著者の二人ならではの視点で、ソーシャルメディア時代だからこそ役割が明確になってきているブログの位置づけや使い方というのがまとまっていますので、今からブログを始めたいという方はもちろん、昔ブログをやってみたけど長続きしなかったという方にも是非読んでみていただきたい本です。
日本においてはブログは日記というイメージが一時定着してしまい、どちらかというとブログは主婦や学生が書くものというイメージを持っている人も増えてしまいましたが、Facebookを使うビジネスマンが増えることによって、ビジネスマンにとってのブログの価値というのは、間違いなく再評価されることになるのではないかと感じています。
ちなみに今回の本出版を記念して、AMNでも5月9日に著者二人によるプロブロガー養成セミナーの開催を支援させていただきましたので、さらにこの本の内容よりも深くブログの活用方法を学びたい方はぜひそちらもどうぞ。
【読書メモ】
■ブログがWebでのホームになる
ソーシャルメディアは、人の集まりやすさや、コミュニケーションのしやすさという点で、ブログよりも優れています。そこで、両者の長所を組み合わせて活用しましょう。
■ブログを書くならば「仲間」と「収入」を得ることをめざそう
■毎日ブログを更新する
・毎日書き続けていると変に気合いが入ることがなくなり、肩の力を抜いてかけるようになる
・ブログが習慣として身につくと「書かないことが気持ち悪い」と感じるようになり、必然的に書き続けられる
■楽しく書くために
・好きなネタだけを選んで書く
・書く以外の作業をできるだけツールで自動化・簡易化して、書くことに集中すること
・無理をしないこと
続きを読む 必ず結果が出るブログ運営テクニック100(コグレマサト、するぷ)を読むと、ソーシャルメディア時代だからこそブログを再評価すべき理由が良くわかると思います。
コミュニティ・オブ・プラクティス (エティエンヌ・ウェンガー他)
 「コミュニティ・オブ・プラクティス」は、共通の専門スキルによって非公式に結びついた人々の集まりの可能性について書いた書籍です。
「コミュニティ・オブ・プラクティス」は、共通の専門スキルによって非公式に結びついた人々の集まりの可能性について書いた書籍です。
2002年に出版された本で昔に読んでいたのですが、あらためて読んでみたので書評抜き読書メモを公開させて頂きます。
この本で描かれているのは共通の専門スキルやコミットメントによって非公式に結びついた人々の集まりである「コミュニティ・オブ・プラクティス(実践コミュニティ)」という概念。
ソーシャルメディアというフレーズが一般的に使われる前に書かれた本ですが、まさにソーシャルメディアによって容易になった組織や企業の壁を越えたコミュニティの可能性について考察されている本だと言えます。
2002年の本という意味で、ある意味古典とも言える本ですが、ツール以前のコミュニティのあり方について考えてみたい方には参考になる点がある本だと思います。
【読書メモ】
■実践コミュニティとは新しい概念ではない
太古の昔から続く、人間初の知識を核とした社会的枠組み
■実践コミュニティの構造
・領域(ドメイン):メンバーの間に共通の基盤を作り、一体感を生み出す
・コミュニティ:学習する社会構造を生み出す
・実践(プラクティス):コミュニティ・メンバーが共有する一連の枠組みやアイデアなど
■実践コミュニティが最も繁栄するのは、組織の目標とニーズが、参加者の情熱や野心と交差する時だ
■コミュニティの七原則
・進化を前提とした設計を行う
・内部と外部それぞれの視点を取り入れる
・さまざまなレベルの参加を奨励する
・公と私それぞれのコミュニティ空間を作る
・価値に焦点を当てる
・親近感と刺激とを組み合わせる
・コミュニティのリズムを生み出す
■成功するコミュニティは参加を強制するのではなく、傍観者のための「ベンチを作る」ことをしている
■コミュニティの発展の五段階
・潜在
・結託
・成熟
・維持・向上
・変容
■専門家のためのコミュニティの目的
・専門分野での一般的な仕事上の問題を協力して解決する
・ベスト・プラクティスを開発し、普及させる
・メンバーが現場の任務で必要とするツールや洞察や手法を開発し「世話」する
・極めて斬新な解決方法やアイデアを生み出す
■コミュニティの変容
・衰弱する
・社交クラブとなる
・分裂や合併
・制度化
■革新的に新しい洞察や展開は、コミュニティとコミュニティの協会で生じることが多い
■有意義な領域を核にしたコミュニティを構築することにより得られる、自己献身と所有者意識には分裂や硬直化、手に負えない複雑性などのリスクを補って余りある価値がある。
■コーディネーター・コミュニティを作る
コミュニティが起動になり、コーディネーターがコミュニティ開発のチャレンジを肌で感じるようになったら、教育と実践開発を組み合わせる
■拡張型ナレッジ・システム
企業の境界の内外の関係や交流によって作られる
 |
コミュニティ・オブ・プラクティス―ナレッジ社会の新たな知識形態の実践 (Harvard Business School Press) エティエンヌ・ウェンガー リチャード・マクダーモット ウィリアム・M・スナイダー 櫻井 祐子 野中 郁次郎 野村 恭彦 翔泳社 2002-12 by G-Tools |
みんな集まれ!ネットワークが世界を動かす (クレイ・シャーキー)
 「みんな集まれ!」は、米国でインターネット関連のコンサルタントとして有名なクレイ・シャーキーがネットの集合知や集団行動の可能性について書いた書籍です。
「みんな集まれ!」は、米国でインターネット関連のコンサルタントとして有名なクレイ・シャーキーがネットの集合知や集団行動の可能性について書いた書籍です。
何かの本で言及されていて気になって買って読んでいたのですが、遅ればせながら書評抜き読書メモを公開させて頂きます。
この本で描かれているのは、ネットによりつながった集団が引き起こす新しい可能性についての考察です。
「ウィキノミクス」から「ドラゴンフライエフェクト」まで、この分野の可能性について考察されている書籍は数多くありますが、この本ではクレイ・シャーキーならではの視点からの考察が展開されているので、また違った視点からネットの集合知やコラボレーションの可能性について考えてみたい方には参考になる点がある本だと思います。
【読書メモ】
■我々がコミュニケーションの方法を変えるとき、社会も変わる。
社会が自らを創造し、継続させるためのツールは、ちょうどミツバチにとっての巣のような中核的な存在である。
■ソーシャルメディアなどのツールは、集団が自己組織化するのを容易にし、個人が正式な管理体制なしに集団に貢献することを可能にした。結果としてそれまで管理のない集団努力が抱えていた、規模や洗練度、影響の及ぶ範囲なっどの限界は、大きく押し広げられることになった。
■集団で行う仕事の難易度順
・共有
・協力
・集団行動
■「馬鹿馬鹿しいほどの集団化の容易さ」(社会科学者セブ・パケット)
グアルディオラのサッカー哲学 (ファン・カルロス・クベイロ)
 「グアルディオラのサッカー哲学」は、バルセロナの監督であるグアルディオラの哲学について書いた書籍です。
「グアルディオラのサッカー哲学」は、バルセロナの監督であるグアルディオラの哲学について書いた書籍です。
Numberの監督特集を読んでいて気になり思い切って買って読んでみたので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。
当然、サッカーのクラブチームの監督の話なので、サッカーに向けての話が中心になるのですが。
組織のリーダーが持つべき心構えや、組織の作り替え方など、企業の中のリーダーを目指す方にも参考になる点がある本だと思います。
【読書メモ】
■グアルディオラはヨハン・クライフのように生まれながらのカリスマ性を持っているリーダーではないと思います。彼の人間性と、これまで培ってきた経験が、今の監督グアルディオラを作り上げているのだと思うのです。
■監督就任を受諾する前に要求した3つの変革
・トレーニングの流れについての大幅な変革
・選手たちのメディカル面とフィジカル面におけるサービスを充実させること
・バルサのプレイスタイルを現代サッカーに沿うものに変更
■「カンテラ時代、グアルディオラの体格は華奢そのものだった。ただ、長い目で見れば、逆にその欠点が長所に転じた。現代サッカーにおいて、フィジカルの弱い選手が生き残る唯一の道は、インテリジェンスしかない。」(ヨハン・クライフ)