 「坂本桂一の成功力」は、ウェブマネーやアルダスなど複数の起業を次々に行ってきた坂本桂一さんの書籍です。
「坂本桂一の成功力」は、ウェブマネーやアルダスなど複数の起業を次々に行ってきた坂本桂一さんの書籍です。
「新規事業がうまくいかない理由」に続いて出版社から献本を頂いていたのですが、読書メモを書けてなかったので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。
成功の定義というのは人によって様々だと思いますが、特にビジネスの世界に生きている方には成功の再定義をするという意味で参考になる点がある本だと思います。
【読書メモ】
■世の中の成功と失敗というのは要するに、さまざまな局面に存在するスレッショルド(閾値)を超えたか超えないかの言い換えにすぎない
■「これが一番」という評価を市場が下した途端、消費者は一斉にその商品や企業を支持し始めるという現象が起きます。
■スレッショルドを超えるために一歩前に出るという生き方が、人として正しいのかどうか私には分かりません。しかし、成功したいと思うなら、そうする以外ないのです。
■結果がでないうちにやめてしまえば、そこまでの努力がすべて無駄になるので、何もしないのと同じことになってしまう
■仕事のスピードをアップするポイント
・仕事の先送りをしないこと
・無駄を省く
■プロとして成功したいなら、24時間、365日できることを何でもするのが当たり前だと思わなければなりません。
日本のウェブの残念度を下げるために、私たちができそうな7つのこと+α
火曜日の「日本のウェブは遅れているのではなく、急速に進みすぎたのではないかという仮説」には、久しぶりに多くの皆さんに、メールやブックマーク、コメント等、いろんなリアクションを頂きました。
ありがとうございました。
最近の私のブログは読書メモばかりを投稿しているのもあり、記事に対するリアクションをもらえる喜びをすっかり忘れていましたが、久しぶりにいろいろと脳みそを揺さぶられる一日でした。
 (本題と関係ないですが、七つの大罪のイメージ)
(本題と関係ないですが、七つの大罪のイメージ)
普段、私のブログはそんなに大勢の方が来られるブログではないのですが、それが一本の記事がピックアップされて多くの人に見てもらえ、反応をもらえるというのが、やはり、はてなブックマークのようなミドルメディアの価値だなーと再確認しましたし、様々なブログでの議論の伝播といい、今回の「日本のウェブは残念」論争で、改めて日本におけるバーチャル・アテネの学堂の可能性みたいなものを垣間見たような気がします。
私自身、2006年頃からAMNというブログをプラットフォームにしたビジネスをする会社に移り、日本のネットやブログをもっと面白くすべき立場の仕事をしているわけですが、今回の議論で、過去にやろうと思っていたことを全然やれていないことを改めて痛感しています。
ちょっと物議をかもしそうな気もしますが、自分がやろうとしていたことを忘れないように、日本のウェブにバーチャル・アテネの学堂的な場所を作るために、私たちが貢献できるのではないかと思っていることを書き出してみます。
アメリカ型成功者の物語 (野口悠紀雄)
 「アメリカ型成功者の物語」は超整理法で有名な野口悠紀雄氏が、シリコンバレーを中心とした地域の成功の背景について考察した本です。
「アメリカ型成功者の物語」は超整理法で有名な野口悠紀雄氏が、シリコンバレーを中心とした地域の成功の背景について考察した本です。
あとがきを担当された滑川さん経由で献本を頂いていたのですが、読書メモを書けてなかったので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。
この本は副題に「ゴールドラッシュとシリコンバレー」とあるように、19世紀のゴールドラッシュから、21世紀の現在に至るまで、サンフランシスコやシリコンバレーで起こった歴史的出来事と現在のシリコンバレーの隆盛にいたる背景を中心に描かれている本です。
最も驚いた話というのが、「19世紀のゴールドラッシュにおける最高の成功者がその理念を結実させた大学を作り、それによって、ITの世界が開けた」という話。(ジョン万次郎がゴールドラッシュがなければ日本に来れなかったかもという話も驚きましたが)
その大学というのが当然、サン・マイクロシステムズ、シスコシステムズ、ネットスケープ、ヤフー、グーグルを生み出したスタンフォード大学なわけです。
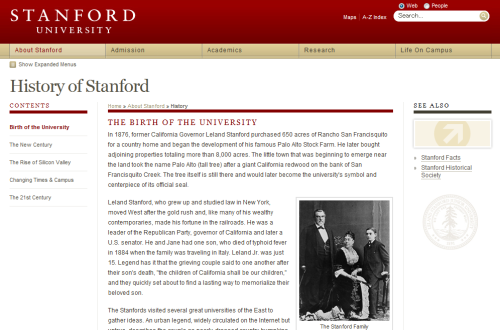
言われてみれば同じ西海岸ですからなるほどという感じもしますが、まさか歴史の教科書で学んだ出来事とインターネットがそういう繋がり方をしているとは思っても見ませんでした。
最近の「日本のWebは残念」論争にもつながる点だと思いますが、シリコンバレーというものが、こういったゴールドラッシュによって引き寄せられた人びとがつくりあげたカルチャーだとか、大学のインフラによって支えられていると思うと、そりゃ日本が10年程度でそう簡単に真似できるものではないなと思い知らされます。
もちろん、個人的には日本はシリコンバレーとは全く別のポジションにあると思うので、シリコンバレーをマネできないからといって敗北宣言をする必要もないと思いますが。
今回の梅田さんのインタビューに始まる論争で、イマイチ日本とアメリカ(特にシリコンバレー)の根本的な違いがピンとこなかったという方には、非常に刺激になる点が多い本だと思います。
【読書メモ】
■カリフォルニアのゴールドラッシュが多くのヒーローを生んだ条件
・自然条件
カリフォルニアの金脈は、地表近くに露出していた
・政治的条件
当時のカリフォルニアは、メキシコ領だった。つまり、政府が事実上存在しない自由の天地だったのである
■日常性への執着
あまりにスケールの大きな問題に直面した場合に、思考が停止する
■(ゴールドラッシュにより)「失敗はあたりまえ。恥ずべきことではない。失敗したらもう一度挑戦すればよい」という考えが、この地に根付いた
■(ジョン万次郎もゴールドラッシュで砂金取りに従事した)
カリフォルニアでの稼ぎがなければ、彼は日本に帰れなかったかもしれない。そうなれば、日本開国の歴史もだいぶ違うものになっていた可能性がある。
「自社メディアの価値を検索連動型広告の費用に換算する」を日経NMに投稿しました。
 日経ネットマーケティングで連載を行っているコラム「カンバセーショナルマーケティングの近未来」に新しいコラムを書きました。
日経ネットマーケティングで連載を行っているコラム「カンバセーショナルマーケティングの近未来」に新しいコラムを書きました。
今回は、検索連動型広告を基準にした、ネットマーケティングの効果測定の考え方について紹介してみました。
不明点や不足点等ありましたら、記事の方でもこちらのブログでも遠慮無くご指摘下さい。
■自社メディアの価値を検索連動型広告の費用に換算する
「前回のコラムでは、CPA(顧客獲得単価)だけでキャンペーンの効果を測るのではなく、「Attention(認知))や「Interest(興味)」など、複数のステップにおける価値も合わせて考えるべきではないか、という話を紹介しました。
ただ、やはりCPAのように売り上げに直接つながる分かりやすい指標を使うのになれていると、売り上げにつながるかどうか分からない「認知」や「興味」の獲得に価値の単価を設定するのは難しいという企業も多いかもしれません。」
※このコラムでは、先日公開したカンバセーショナルマーケティングの講演資料でまとめた話の掘り下げだとか、実際にソーシャルメディアを活用したマーケティングを実践する際のステップなどを書いていければと思っています。

日本のウェブは遅れているのではなく、急速に進みすぎたのではないかという仮説
ITmediaの岡田さんによる梅田さんのインタビューに端を発した、「日本のWebは残念」論争ですが、梅田さんの人物考察が一段落するのに併行して、いろいろと日本のウェブの特徴についての考察が始まっているようです。
せっかくの機会なので自分の考えも、まとめておきたいと思います。
 (海部さんのエントリに刺激を受けて、アテネの学堂のイメージ)
(海部さんのエントリに刺激を受けて、アテネの学堂のイメージ)
今回の議論に目を通していて、個人的に気になったのは下記のあたり。
・nobilog2: Web日本語文化圏、私なりの考察
・梅田氏と「アテネの学堂」 – Tech Mom from Silicon Valley
・日本のネットが「残念」なのは、ハイブロウな人たちの頑張りが足りないからかも知れない(追記あり):小鳥ピヨピヨ
・無名が主役になれる日本は世界のパラダイス(たとえばラーメン) – [ f ]ふらっとどらいぶログ
いずれも米国のネットに対して、日本のネットが梅田さんに残念と評されるようになった背景等を考察していて興味深いです。
私自身、アルファブロガー投票企画とかをやっていたように、海部さんがいうところのバーチャル・アテネの学堂的な、梅田さんやいちるさんがいうところのハイブロウな人たち(定義を良く理解してないので、あまりこの言葉は使いたくないのですが)による日本のネットが広がることを期待していた人間です。
ただ、最近いろんな議論を、メディアの方やウェブサービス系の方々とする過程で、個人的に生まれてきている仮説が、タイトルに書いた「日本のネットは遅れているのではなく、急速に進みすぎたのではないか」という話です。
そのポイントは、下記の3つ。
■1.日本はやっぱりブログ(日記)を書いている人が明らかに多い?
■2.芸能人によるネット活用は、日本の方が進んでいる?
■3.英語圏も、衆愚化が進み始めているらしい?
ソーシャル消費の時代 (上條 典夫)
 「ソーシャル消費の時代」は電通ソーシャル・プランニング局長の上條典夫氏が2015年の日本の消費がどうなるかを予測している書籍です。
「ソーシャル消費の時代」は電通ソーシャル・プランニング局長の上條典夫氏が2015年の日本の消費がどうなるかを予測している書籍です。
先週のワールドビジネスサテライトでも取り上げられていたようですね。
出版社から献本を頂いていたのですが、読書メモを書けてなかったので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。
未来の予測というのは、長期の予測はいろいろあっても実際のビジネスで重要なのは3~5年先。
そう言う意味でこの本が取り上げている2015年の予測というのは、なかなか興味深いところをついているように感じます。
この本ではネットから環境、高齢化等、各事業分野における様々な予測がたくさん詰まっていますので、未来に向けて視野を広げてみたいという方にはヒントになる点がある本だと思います。
下記に著者のインタビューも掲載されていますので、参考にどうぞ。
・『ソーシャル消費の時代』を書いた上條典夫氏(電通ソーシャル・プランニング局長)に聞く(1)
【読書メモ】
■ケータイ・ネイティブ
日本独自のケータイカルチャーを共有する世代
■10代の若者たちがブログやSNSでたどるコミュニケーションのパターン
・日記を書く
・友人のコメント
・御礼を書く
・相手のページを訪問する
■モノ余りの時代には、モノそのものより、モノがココロと結ばれるまでの「過程段階」や「波及効果」の価値が高まる。
■21世紀の3Cは「コミュニケーション、クリエイション、カルチャー」
モノによって誰かと「つながる=コミュニケーション」、そのモノが自己表現の個性を「創れる=クリエーション」、モノの周りで仲間と共通の世界観に「ひたれる=カルチャー」の部分に時間を費やし、お金を消費する傾向が強まっていく
■物語消費
物語消費においては、主人公=私が、より明確に消費というドラマを追求していく。つまり、それは「私が主役」の「私小説消費」ともいえるものだ。