昨日、先日ご紹介したアルファブロガー・アワード2008の関係で、livedoorブログさんのピックアップテーマを使わせて頂く機会がありました。
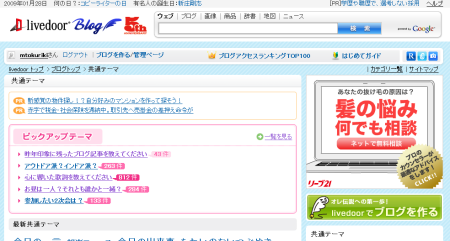
ピックアップテーマとは、livedoorブログの利用者の方向けに、日々ライブドアさんがお題を出して投稿を募集しているもの。
私のお題はマニアックすぎたせいか、まだ投稿量は少ないのですが、日々数百を超える投稿が集まっていて、いまや総投稿数が290万件を超えていると言うから凄いです。
こうやって、ブログサービス毎のコミュニティがあったりするもんなんですね。
個人店舗的なMovable Type歴が長くなってしまった自分からすると、なんだか不思議な感覚でした。
で、ちょうどlivedoorブログ自体がリニューアルだったと紹介してもらったので、あわせて管理画面を久しぶりに覗いて見ました。
実は、このtokuriki.comの前身は元々livedoorブログだったりするんです。
(その後、JUGEM→ロリポブログ→Movable Typeという変遷を辿っています。)
管理画面をキャプチャするとこんな感じ。

なんだかお洒落になってます。
ちなみに古い管理画面はこんな感じ。
「広告を活用するのは最後の手段と考えてみよう」を日経NMに投稿しました。
 日経ネットマーケティングで連載を行っているコラム「カンバセーショナルマーケティングの近未来」に新しいコラムを書きました。
日経ネットマーケティングで連載を行っているコラム「カンバセーショナルマーケティングの近未来」に新しいコラムを書きました。
今回も、前回に引き続き私なりのAISASの考え方の話を書いています。
不明点や不足点等ありましたら記事の方でもこちらのブログでも遠慮無くご指摘下さい。
■広告を活用するのは最後の手段と考えてみよう:日経ビジネスオンライン
「 前回のコラムでは、「広告で売れないからクチコミで何とかしたい」という発言は、その発言をしている時点で、かなり厳しい状況ではないかという話をしました。
ただし、大ヒットする製品でなければクチコミが広がらないかというと、そんな話ではありません。
今回はクチコミを意識したマーケティングを成功させる上で、鍵となるチェックポイントについて紹介したいと思います。 」
※このコラムでは、先日公開したカンバセーショナルマーケティングの講演資料でまとめた話の掘り下げだとか、実際にソーシャルメディアを活用したマーケティングを実践する際のステップなどを書いていければと思っています。

経営の未来 (ゲイリー・ハメル)
 「経営の未来」は、インターネット時代の新しいマネジメントについて詳細な考察をしている書籍です。
「経営の未来」は、インターネット時代の新しいマネジメントについて詳細な考察をしている書籍です。
アンカテのessaさんの書評に影響されて昨年購入して読んでいたのですが、読書メモを書けてなかったので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。
一般的にマネジメントというと、経営「管理」と訳されることが多く、「管理者」という言葉に代表されるように管理の重要性が強調されてきた印象があります。
ただ、この本に書かれているのはいわゆるそう言った今までの管理的マネジメントではなく、イノベーションを生み出し続ける組織になるための新しいマネジメントです。
特にグーグルの経営管理方式についても、かなり突っ込んで紹介されていますので、いわゆる大企業の人たちだけでなく、インターネット企業につとめている人にも参考になる点が多々あると思います。
「ウィキノミクス」や、「ヒトデはクモよりなぜ強い」に刺激された人が、「ではどうすればよいか」を考えるのに非常に役に立つ、これからの経営者にとっては必須の本だと思います。
【読書メモ】
■近代経営管理の仕組みは、気ままで独断的で、自由な精神を持つ人間を標準やルールに従わせはするが、それによって膨大な量の想像力と自主性を無駄にする。
■経営管理イノベーション
経営管理の仕事を遂行する手法や従来の組織の形を大幅に変え、なおかつ、そうすることによって組織の目的を推進するあらゆるものをいう。
■経営管理の仕事は計画策定、組織づくり、指揮、調整、および管理である(アンリ・ファヨール)
■経営管理イノベーションが競争優位を生み出す条件
・長年信じられてきた正当理論を否定する、まったく新しいマネジメント原理に基づいている
・体系的で、一連のプロセスやメソッドを含んでいる
・前進のペースが時とともに増していく、進行中の加速度的な発明プログラムの一環である
■イノベーションの階層
・経営管理イノベーション
・戦略イノベーション
・製品/サービス・イノベーション
・業務イノベーション
■「凡庸な問題やつまらない問題は、凡庸な答えやつまらない答えを生み出す。だから大きく考えることが必要なのだ。」(ピーター・メダワー郷)
■本質的で賞賛に値する問題に取り組むための問い
・あなたの会社がこの先直面することになる新しい課題は何か。
・あなたの会社がうまくやれそうにない難しい両立課題は何か
・あなたの会社の理論と現実のギャップのうち、最大のものは何か
・あなたは何に憤りを感じているか。
ヒトデはクモよりなぜ強い (オリ・ブラフマン)
 「ヒトデはクモよりなぜ強い」は、分散型組織の特徴や要素について具体的な事例を元に考察している本です。
「ヒトデはクモよりなぜ強い」は、分散型組織の特徴や要素について具体的な事例を元に考察している本です。
koyhogeの小山さんに勧められて、昨年購入して読んでいたのですが、読書メモを書けてなかったので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。
先日紹介した「ウィキノミクス」同様、この本で考察されているのも「フラット化する世界」ならではの新しい組織の可能性なのですが、個人的には分散型組織と集権型組織の対峙の事例としてアパッチ族とスペイン軍であったり、アルカイダとアメリカ合衆国であったりと、新旧まじえた考察がされているのが非常に興味深かったです。
当然、ナップスターやイーベイ、ウィキペディアなど、ネット企業の事例も多数出てきますので、インターネットを活用した分散的なアプローチで、巨大企業がひしめく市場にチャレンジしている企業にとっては、参考になる点が非常に多い本だと思います。
【読書メモ】
■分権についての重要な8つの法則
・分権型の組織が攻撃を受けると、それまで以上に開かれた状態になり、権限をそれまで以上に分散させる。
・ヒトデを見てもクモだと勘違いしやすい
・開かれた組織では情報が一カ所に集中せず、組織内のあらゆる場所に散らばっている
・開かれた組織は簡単に変化させることができる
・ヒトデたちには、誰も気づかないうちに、そっと背後から忍び寄る性質がある
・業界内で権力が分散すると、全体の利益が減少する
・開かれた組織に招かれた人たちは、自動的に、その組織の役に立つことをしたがる
・攻撃されると、集権型組織は権限をさらに集中させる傾向がある
■ヒトデとクモを見分ける方法
・誰かひとり、トップに責任者がいるか?
・本部があるか?
・頭を殴ったら死ぬか?
・明確な役割分担があるか?
・組織の一部を破壊したら、その組織が傷つくか?
・知識と権限が集中しているか?、分散しているか?
・組織には柔軟性があるか、それとも硬直しているか?
■信頼感とコミュニティ
クレイグズリストを使ってタダで箱を手に入れるということは、クレイグズリストというコミュニティにちょっとした借りができるようなものだ。
■開かれた組織では、最も重要なのはCEOではなく、組織のリーダーが、組織を構成するメンバーをどれだけ信頼し、その自主性に任せるかなのだ。
「広告で売れないからクチコミで何とかしたい、は可能なのか?」を日経NMに投稿しました。
 日経ネットマーケティングで連載を行っているコラム「カンバセーショナルマーケティングの近未来」に新しいコラムを書きました。
日経ネットマーケティングで連載を行っているコラム「カンバセーショナルマーケティングの近未来」に新しいコラムを書きました。
今回も、前回に引き続き私なりのAISASの考え方の話を書いています。
不明点や不足点等ありましたら記事の方でもこちらのブログでも遠慮無くご指摘下さい。
■広告で売れないからクチコミで何とかしたい、は可能なのか?:NBonline(日経ビジネス オンライン)
「「この製品、広告を流してもなかなか売れないんですが、クチコミで何とかなりませんか?」
製品の販売に苦労している企業から、よく聞かれるのがこの質問です。
前回のコラムでは、効率的にクチコミのサイクルを回すことができれば広告費をそれほどかけずに成功可能という話を紹介しました。 」
※このコラムでは、先日公開したカンバセーショナルマーケティングの講演資料でまとめた話の掘り下げだとか、実際にソーシャルメディアを活用したマーケティングを実践する際のステップなどを書いていければと思っています。

ウィキノミクス (ドン・タプスコット)
 「ウィキノミクス」は、いわゆるウェブ2.0的な世界における特徴的な現象や、その原理について考察した本です。
「ウィキノミクス」は、いわゆるウェブ2.0的な世界における特徴的な現象や、その原理について考察した本です。
昨年購入して読んでいたのですが、読書メモを書けてなかったので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。
すでに多数のブログで書評が書かれているように、この本は「フラット化する世界」や「ウェブ進化論」などで描かれている変化によって、具体的にどのような新しい仕組みが生まれつつあるのかということを豊富な事例と共に解説した本です。
今年は、個人的にもクラウドソーシング的なアプローチにチャレンジしたいと思っているのですが、そういったネットならではの新しいアプローチに興味がある方はこの本は必読書だと思います。
【読書メモ】
■ウィキノミクス
・ピアプロデューサー:ビットでできた製品の構築にはオープンソース型のやり方が利用できる
・アイデアゴラ:アイデアと革新の備えある人材のグローバル市場にアクセスすれば、問題解決能力を拡大することができる
・プロシューマー:価値創造に参加できるだけのツールをユーザーに与えれば、とてつもない革新の源となる
・新アレクサンドリア人:コラボレーションによる科学という新しいやり方により、技術革新の加速とコストの削減ができる
・参加のプラットフォーム:パートナーによる大規模コミュニティが協力関係で結ばれたエコシステムとなって価値を生む。
・世界工場:企業の境界も国境も越えて人的資本を活用し、物理的な物の設計や組み立てを行うことができる
・ウィキワークプレイス:さまざまな形で組織階層を打ち破り、意欲を高め、イノベーションを増やすことができる
■可能性と危険性
小さくてオープン、もちつもたれつの世界はダイナミックで高い活力をもつ可能性があると同時に、テロや犯罪が増えるおそれもある。
■「集産主義には強制と中央集権が伴う。集合活動は自由意志による選択と分散型協調が特徴である」(ハワード・レインゴールド)
共産主義が個人の独立的思考を抑圧するのに対し、マスコラボレーションとは、個人や企業が広く分散されたコンピュータと通信技術を活用し、ゆるやかで自発的な協力関係を通じて共有する成果を得ることなのだ。
■ウィキノミクスの4本の柱
・オープン性
・ピアリング
・共有
・グローバルな行動