さて、すっかり告知が遅くなってしまったのですが。
2004年から毎年続けていたアルファブロガー・アワード(旧:アルファブロガーを探せ)ですが、今年は思いっきり趣向を変えて、ブログ記事大賞ということで、ブログ単位ではなく記事単位の投票で開始しました。
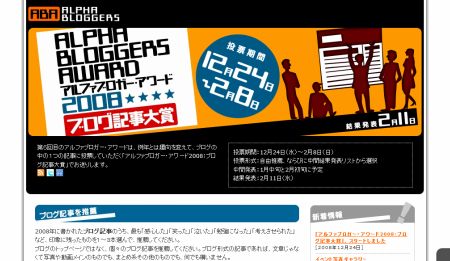
実は記事単位での投票というのは、最初の2004年のアルファブロガーを探せの時にも試みていた幻の企画です。
当時は、ただでも無名の企画だったので、ブログ毎の投票を集めるのが精一杯で、記事毎の投票はほとんど有意義な数が集まらず、結果発表すらしなかったという経緯がありました。(その節は、投票頂いた皆さん、本当に申し訳ありませんでした。)
ただ、記事毎の投票をやってみたらという意見は多数いただいていましたし、現在では2004年に比べると、ソーシャルブックマークとかブログ検索とか、1年を振返るためのツールも充実していますし、とにかく一度やってみようということで、実施に至った次第です。
安定して人気のあるブログを運営するには日々コンスタントに記事を書いている必要がありますが、一方で一本の記事だけでも突出して印象に残るブログというのもあると思います。
是非、2008年1年を振返って、投票してみていただければ幸いです。
また、ブログをお持ちの方はせっかくですので、是非どの記事に投票したか、ブログで公開してみて下さい。
ということで、私が2008年、もっとも印象に残った記事は下記の3つです。
・Google の中の人への手紙 [日本のストリートビューが気持ち悪いと思うワケ] – higuchi.com blog
なんといっても2008年個人的にもっとも印象に残ったのはこちらの記事です。
内容ももちろんなのですが、特に印象に残ったのは以前ブログで書いたように、この記事が、essaさんやGlobal Voices Onlineの翻訳などをきっかけに国境を越えて伝播したこと。
日本語と英語の壁を越えて、それぞれの文化や価値観に対する議論が行われるのは非常に印象的で、いろんな意味で刺激を受けたエントリーでした。
・【秋葉原無差別殺傷】人間までカンバン方式 – 何かごにょごにょ言ってます
次に印象に残ったのはこちらの秋葉原無差別殺傷事件に関連して、はてなブックマークで1000を超えて話題になったこちらの記事です。
普段、ネガティブなニュースはできるだけ見ないように心がけているので、秋葉原の事件もあまり詳しくはウォッチしていなかったのですが、この記事を通じて一般に報じられているような表層的な面だけではなく、現在の日本が抱えている根本的な問題について本当に考えさせられました。
また、この記事の前に書かれた記事は2007年8月のようですから、1年近く休眠していたブログに久しぶりに書かれたブログの記事が、ちゃんと広く伝わったという意味でも、印象的な出来事でした。
・俺達ちゃんと政治もハックしているよ – 雑種路線でいこう
最後にあげたいのは、この記事も含めた一連の楠さんの有害サイト規制に対する「情報発信」と「行動」です。
楠さんは2008年の1月に「有害サイト規制の前に議論すべきこと」という記事をアップしているのですが、その後も積極的に安易なネット規制に対して警鐘を鳴らし続け、それだけでなく実際に企業や様々な人たちを動かす活動をされていました。
個人的にも、ついつい政治や規制などに対しては無力感を日々感じている人間ですが、文句を言っているだけでなくちゃんと行動しなければと思わされた記事でした。
(WOMマーケティング協議会の設立にコミットしているのも、少なからず楠さんのこうした活動に影響を受けたことがあります。)
ということで、記事を振返って投票するのは大変だと思いますが、是非、皆さんも去年一年を振返って、印象に残った記事を教えていただければ幸いです。
ご協力のほどよろしくお願いします。
(サイトからの投票も是非是非忘れずに!)
「Shareしてくれる人の存在がクチコミマーケティングの成否を決める」を日経NMに投稿しました
 日経ネットマーケティングで連載を行っているコラム「カンバセーショナルマーケティングの近未来」に新しいコラムを書きました。
日経ネットマーケティングで連載を行っているコラム「カンバセーショナルマーケティングの近未来」に新しいコラムを書きました。
今回は、前回に引き続き私なりのAISASの考え方の話を書いています。
不明点や不足点等ありましたら記事の方でもこちらのブログでも遠慮無くご指摘下さい。
■Shareしてくれる人の存在がクチコミマーケティングの成否を決める:NBonline(日経ビジネス オンライン)
「 前回のコラムでは、「Attention(注意)」「Interest(興味)」「Search(検索)」「Action(購買)」「Share(情報共有)」の五つのステップからなる消費行動モデル「AISAS」を、単純な時間軸の流れとして見るのではなく、自社の製品やサービスの潜在的な見込み顧客のレイヤーとしてピラミッドで見るべきという話を紹介しました。
AISASをピラミッドで見た場合、重要になるのがピラミッドの頂点にあるShare(情報共有)の部分です。 」
※このコラムでは、先日公開したカンバセーショナルマーケティングの講演資料でまとめた話の掘り下げだとか、実際にソーシャルメディアを活用したマーケティングを実践する際のステップなどを書いていければと思っています。

MSN産経ニュースでインタビューをして頂きました。
MSN産経ニュースの「アルファブロガーに聞く」という企画でインタビューをして頂きました。
個人的にはMSN産経ニュースのような、一般ニュースのエリアにアルファブロガーという言葉が踊っているのが実に不思議な感覚だったりしますが、一般の方からするとアルファブロガーどころか、いわゆるブログ関連の話も縁遠かったりすると思うので、こういう機会は実に貴重ですね。
今年は、ブログ界隈でもちょっと新しい取り組みをはじめられればと思います。
・アルファブロガーに聞く「ブログの未来」(上)アジャイルメディア・ネットワーク 徳力基彦取締役 (1/3ページ) – MSN産経ニュース

徳力の2009年の抱負

長年続けていると恥ずかしさも無くなってくるものですね。
今年も淡々と公開したいと思います。
2008年は、会社を移った2007年ほどの大きな環境の変化はなかったのですが、本当にいろんなことへの試行錯誤が続いた年でした。
去年書いた抱負を見ると、ビデオブログの実践とか書いているのですが、結局、年の後半それどころではなくなってしまい、インタビューに協力頂いた方に本当に申し訳ない限りです。
今年は、あまり風呂敷を広げすぎずに、まずはAMNでの本業に集中する年にしようと思います。
とはいえ、忘れていることや足りないことも多いかと思いますので、お会いしたときとか何かの機会に、アドバイスとか、はっぱをかけてもらえると幸いです。
グランズウェル (シャーリーン・リー)
 「グランズウェル」は、米国においてソーシャルメディアの専門家として非常に有名なシャーリーン・リーが書かれた書籍です。
「グランズウェル」は、米国においてソーシャルメディアの専門家として非常に有名なシャーリーン・リーが書かれた書籍です。
翻訳をされた伊東さんに献本を頂いていたのですが、読書メモを書けてなかったので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。
事例も抱負で、体系だってまとめられているので、ブログを始めとするソーシャルメディアを活用するマーケティングに興味がある方にはバイブルになる可能性がある本だと思います。
オススメです。
個人的にも、これまでカンバセーショナルマーケティングという言葉で表現しようとしていた世界感が、この本にしっかり整理されていると感じているので、来年はこの本を参考に日本向けのグランズウェル的アプローチを真剣に考えたいと思います。
【読書メモ】
■ストライサンド効果
インターネットからコンテンツを削除しようとして、逆に広めてしまう現象
■グランズウェルを生んだ3つの力の衝突
・人間
・テクノロジー
・経済学
■ファストレーンは、GMのコミュニケーションを一変させた
業界紙や高額なテレビCMだけが、顧客、ディーラー、従業員、投資家にメッセージを伝える方法ではない。GMは、彼らに直接語りかけるチャネルを手に入れたのだ。
■ソーシャル・テクノグラフィックス・プロフィール
・創造者(Creators)
・批評者(Critics)
・収集者(Collectors)
・加入者(Joiners)
・観察者(Spectators)
・不参加者(Inactives)
■グランズウェル戦略の4段階のプロセス「POST」
・人間(People):顧客は、どんなテクノロジーを使う傾向があるのか
・目的(Objectives):ゴールは何か
・戦略(Strategy):自社と顧客の関係をどう変えたいのか
・テクノロジー(Technology):どんなアプリケーションを構築すべきか
■グランズウェル戦略の5つの目的
・傾聴戦略:顧客理解を深める
・会話戦略:自社のメッセージを広める
・活性化戦略:熱心な顧客を見つけ、彼らの影響力を最大化する
・支援戦略:顧客が助け合えるようにする
・統合戦略:顧客をビジネスプロセスに統合する
■グランズウェル戦略へのアドバイス
・小さく始める
・グランズウェル戦略がもたらす戦略を考え抜く
・高い地位にいる人物を責任者に据える
・テクノロジーの選択とパートナーの選択は慎重に
情報革命バブルの崩壊 (山本一郎)
 「情報革命バブルの崩壊」は、切込隊長BLOGでお馴染みの山本一郎さんの書籍です。
「情報革命バブルの崩壊」は、切込隊長BLOGでお馴染みの山本一郎さんの書籍です。
献本を頂いていたのですが、読書メモを書けてなかったので、書評抜き読書メモを公開させて頂きます。
金融危機がインターネットに与える影響だとか、来年以降のネット業界の課題とか可能性とかが気になる方には、参考になる点が多い本だと思います。
【読書メモ】
■情報革命の本質とは、情報そのものが増えたわけではない。情報へアクセスする方法の効率が良くなっただけである。
■ネット社会における価値は「情報」と「名声」によって集約され、価値のある情報がもたらされる島や、社会的に知見の高いとされる名声がある島は大きくなり、多くのネット人口を養う。一方、ある情報の価値というものは、その特定の分野に関心を持っている人においてのみ高まり、関心のない人は見向きもしない。
■ネット社会が一般人の購買に強い影響力を与えていることはマーケティング上多くの事例を蓄積する中で分かりつつあるが、一方で多くのネット上の工作、煽動の技法の確立という悪しき側面も見受けられるようになった。
■ネットの元から持つアングラ的なスキルや方法論が、そのままネット社会の成長と共に現実社会の消費行動に大きな影響を与え始めている。
■ソースロンダリング
ネット内でちょっとした揚げ足取りのような議論をわざと湧かせ、問題であるとネット内で批判の火をつけようとし、ある程度コメント数が揃ったところでJ-CASTに代表されるネット内メディアやZAKZAKなど夕刊紙のサイトでネット内のトピックスとして取り上げることから、社会的な炎上は始まる。
■ネット内でなぜバッシングが起きやすく、現実社会に対して批判的な言論が成立し支持されやすいのか
・ネットでのこれらの言論や風評を、具体的な検証なしに鵜呑みにする程度の社会知識しかない人がネット社会での議論で声が大きいこと
・既存のマスコミがネットに進出する過程で、ネットから情報を拾って書かれる記事が急増したこと
・私たちは私たちの見知った、専門とするもの以外は、情報の真贋など判断がつかず、自分の関心領域から外れたものの価値は、過大評価するか過小評価するしかできない、という点
■情報化社会は国民の総専門家化を促すものであり、一人の人間が持つ情報量に限りがある以上、社会にいる人間同士が価値観や考え方を共有したり相互理解することの妨げになりかねない。しかも、これを押し止めることはできない。
■我が国でも場合によってはネットの無料文化自体をどう収束させ、適正な費用をユーザーから徴収し、ネット業界全体で按分していくべきかという議論は政策レベルで為されなければならないだろう。
■ネット界隈が一般社会の価値観や秩序の枠組みに取り戻され、普通の社会の延長線上にネットがあるのであって、ネットが必ずしも「あちら側」の踏み進むべきフロンティアとは限らない、ということを、良く理解するべきだと考えるのである。
■この世界間の競争に自分たちが不利とならないよう、どのようなルールを加えるべきか、どうすれば加えられるのか、それを学ぶことこそが、混乱期を乗り切るもっとも重要なエッセンスにほかならない。