 「マーケティング戦略の未来」は、タイトル通りマーケティングの未来について考察している書籍です。
「マーケティング戦略の未来」は、タイトル通りマーケティングの未来について考察している書籍です。
献本を頂いていたので、遅ればせながら書評抜き読書メモを公開させて頂きます。
この書籍では著者グループであるブーズ・アンド・カンパニーが、俯瞰的な視点からマーケティングの未来について分析されています。
特に米国と日本の広告代理店の位置づけや変化の違いについての考察は、第三者ならではの視点から分析されていますので面白いです。
マーケティングの未来を考えてみたいという方はもちろん、マーケティング業界の構造自体を学びたいという方にも参考になる点がある本だと思います。
【読書メモ】
■消費者は、買いたい時に情報を検索すればいいということに気づき、当分その商品は買わないという状態で広告に接しても、その内容を記憶にとどめようとしなくなった
■デジタル時代の新たなマーケティング環境には「常時接続(Always On)という特徴がある
■スーパーCMO
従来のマーケティング担当役員たちよりもメディアに精通し、より広告の効果測定を重視している。単にマーケティング・キャンペーンを管理したり、広告業者を監督したりするだけでなく、会社の業績やイノベーション、成果を伸ばすことにこだわる
■ナイキのマーケティング戦術は、洒落たキャッチフレーズや印象的なロゴをちらつかせることから、消費者の体験を重視するものに変わったのである
投稿者: 徳力 基彦
ネットも店舗も乗り入れ、事業区分消える を日経MJに寄稿しました。
すっかりご紹介が遅くなりましたが、先週、日経MJ「ECの波頭」に寄稿しているコラムが掲載されましたのでお知らせします。
境界線をまたいだ事業をされている方からすると当然の話だとは思うのですが、意外に縦割りに考えている方がまだまだ多いようなので、あえて書いてみました。
9月15日にファッションのECサイトとして有名な「ゾゾタウン」が「ZOZOCOLLE(ゾゾコレ)」というイベントを幕張メッセで開催した。ゾゾタウンがこういったリアルイベントを開催するのは初めてだが、2日間で1万人が来場し、約1億5000万円を売り上げたという。
ゾゾタウンの主戦場はオンラインであり、ショップ数430以上、ブランド数1900以上を取り扱う日本最大級のファッション通販サイトだ。ここまで成功したのは、オンラインの強みをいかしているからこそであり、そのファッション通販サイトがわざわざリアルイベントを開催するのを意外に感じる方も少なくないかもしれない。
《ポイント》
(1)ゾゾタウンやニコニコ動画が数万人規模のイベントを開催。
(2)ネット事業者によるリアルイベントや店舗展開は増える傾向にある。
(3)ネット事業者か既存事業者かという分類が無意味になりつつある。
続きは日経新聞のサイトでご覧ください。
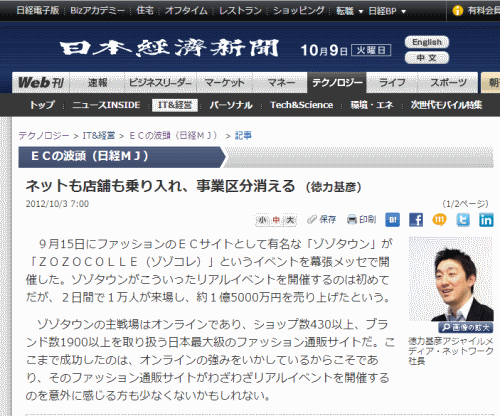
グリーさん、モバゲーさん、「ゲーム」という言葉が「ギャンブル」や「麻薬」と同義語にならないように、是非ソーシャルゲームの明るい未来のビジョンを語って下さい。
今週火曜日のNHKでソーシャルゲームの課題についての特集が放送されていたようです。

内容については、下記のページに大筋がまとめられているので、興味がある人は読んでもらえればと思いますが、まぁ要はコンプガチャ問題が収束した後もソーシャルゲームの問題は終わっていないという趣旨の特集です。
・ソーシャルゲーム 急成長のかげで – NHK クローズアップ現代
先月末にもMrサンデーか何かで、似たような特集が組まれていて中国のネットゲーム廃人が刃物振り回したり、軍隊みたいな厚生施設に連れて行かれる様子が生々しく紹介されていましたが。
まだまだメディアによるこうした「ソーシャルゲームの影」的な特集はしばらく続きそうです。
こういった報道を見て個人的に悲しくて仕方が無いのは、完全にゲームが、違法なギャンブルや麻薬と同じ社会問題として取り上げられてしまっているということです。
今更改めてカミングアウトすることでもありませんが、私はゲームが三度の飯より大好きです。
小学生の頃は、友達の家でファミコンをするために友達の家に入り浸っていましたし、中学、高校は将来PCのスキルが大事だからとNECの98を買ってもらったのを良いことに、パソコンでゲームばかりやってました。
Dungeons & DragonsというテーブルトークRPGも毎週のようにやっていて、親にはゲームばかりするなといつも怒られていました。
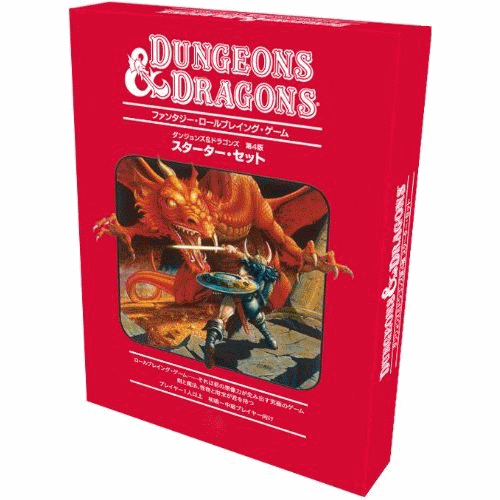
当然大学生の一人暮らしではスーファミに大変お世話になりましたし、下記の記事で告白したように社会人になってからも何度かゲーム廃人になりかけています。
・私が思いっきりハマって、人の道を踏み外しそうになってしまったゲームベスト5
私が生涯の理想としている人は、伊藤穣一さんなんですが、何でかというと伊藤穣一さんがMITメディアラボの所長になるような凄い人だから、だけではなく、一時World of Warcraftというゲームにはまっていて、ゲームのメッセージ機能を使わないと連絡が取れなかったという逸話を目にしたからです。
続きを読む グリーさん、モバゲーさん、「ゲーム」という言葉が「ギャンブル」や「麻薬」と同義語にならないように、是非ソーシャルゲームの明るい未来のビジョンを語って下さい。
クラウドファンディングの最大の魅力はお金を集められるところではなく、応援を可視化できるところにあるのかもしれない
先日の「今更ブログ始めるのって時代遅れですよね?という質問に対する自分なりの回答」という記事には多くの方にリアクション頂き有り難うございました。
お陰様で、プロブロガーセミナーのプロジェクトは最低催行金額の10万円を突破することができましたので、セミナー自体の開催を確定することができました。
ご協力頂いた皆さん、本当にありがとうございました。

先日のブログに書いたFacebookやツイッターなどの「フロー」系のソーシャルメディアに対して、ブログは「ストック」の価値があるという話は実はそこら中で話し続け、書き続けているつもりですし、ブログを実際にやっている方からすると当然すぎる話だったりすると思うんですが、改めて言い続けることの大事さを感じている次第です。
で、今回は初めて自らCAMPFIREでクラウドファンディングの仕組みを使ってみて、思ったところを書いておこうと思います。
今回のプロブロガーセミナーが、セミナーであるにも関わらず、わざわざクラウドファンディングを利用したのは、先日の記事に書いたように支援表明の可視化が目的です。
有料セミナーを開催したいだけなら普通にイベントレジストとかPeatixで申込フォーム作ってチケット売った方が明らかに手間もかからないし安いんですが。
セミナーの申込フォームだと、来れる、か、来れない、の二択しか基本的に判断できません。
それがクラウドファンディングにおいては、複数の段階を設けることで皆さんの温度感を感じることができるのが改めてメリットだなと感じています。
例えば40人を募集するセミナーだと、通常のセミナーなら40人が集まったらそこで締め切り。「チケット全部売れて良かったね」で終了です。
それが今回のようなクラウドファンディングの仕組みでやると、例えば実際当日来る人は同じ40人でも、当日別件があって参加できないから動画だけでも見たい、とか、東京には遠くて来れないんだけどオンラインで見たい、とか、段階をおった形でニーズを可視化することができます。
極端な話、実際に当日来れる人は5人なんだけど、オンライン視聴希望が100人集まったから必要費用をまかなえて開催できる、とかがあり得るわけです。
特に大きな違いだな、と思うのがパトロンになってくれた人たちの応援コメント。

続きを読む クラウドファンディングの最大の魅力はお金を集められるところではなく、応援を可視化できるところにあるのかもしれない
今更ブログ始めるのって時代遅れですよね?という質問に対する自分なりの回答
先週末にAMNでは、コグレさんとするぷさんが講師のプロブロガーセミナーの募集を開始しました。

セミナーの開催なのに何でわざわざCAMPFIRE使うの?と思われている方もおられるかもしれないので、ちょっと背景をご紹介しておきたいと思います。
私は恥ずかしながら名刺にブロガーと肩書きが入っている人間なので、名刺交換したときに自然とブログの話が話題になることが多くあります。
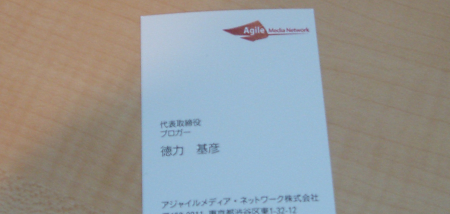
そんな時に結構聞かれるのがこの記事のタイトルにも入れた
「昔からブログやってみようかと思ってたんですけど、今更ブログ始めるのって時代遅れですよね」
という質問です。
日本では、流行語大賞に代表されるような毎年何かが流行って次の年には古いモノとして扱われる、というのがソーシャルメディアの世界でも繰り返されてきていますから、2005年に流行語大賞にノミネートされた「ブログ」が古いものと扱われてしまうのは、個人的にも良くわかります。
なにしろ一昨年流行語大賞に「なう」がノミネートされたばかりのツイッターでさえ、人によっては過去のサービス扱い。
気の早い人だと今年LINEが流行ったのをもとに、昨年大きな話題となったFacebookを既に古いサービスと位置づけているようです。
ただ実際には一口でソーシャルメディアといってもサービス毎に機能や特性、利用者のコミュニティが違いますし、必ずしも一つのサービスが排他的なモノではありません。
特にいわゆるツイッターのようなマイクロブログとFacebookやmixiのようなSNSに比べると、普通のブログというのは大きな違いがあります。
それが今回のセミナーでも重要なテーマとなってくる「フローとストック」です。
顧客ロイヤルティを知る究極の質問(フレッド・ライクヘルド) は、NPS(ネットプロモータースコア)を理解するための必読本です。
 「顧客ロイヤルティを知る究極の質問」は、ベイン・アンド・カンパニーのフレッド・ライクヘルド氏が書いたNPSの解説書籍です。
「顧客ロイヤルティを知る究極の質問」は、ベイン・アンド・カンパニーのフレッド・ライクヘルド氏が書いたNPSの解説書籍です。
かなり前に読んでいたのですが、遅ればせながら書評抜き読書メモを公開させて頂きます。
この本は、最近ソーシャルメディア関連の効果測定の手法としても話題に出ることが増えてきたNPS(ネットプロモータースコア)のバイブルということができる本です。
私個人がNPSについて興味をもったのは3年ぐらい前にツイッター関連のイベントでデルさんと無印良品さんとパネルディスカッションをご一緒した際に、NPSを指標としているという話を聞いたからなのですが、実は米国ではNPSはかなり多くの企業の経営指標として使われるようになっていて、人事評価と連動させている企業も少なくないようです。
NPS自体の解説はこちらのページに出ていますが「ネットマーケティング・キーワード – NPS とは:ITpro」、要は「あなたはそれを友人や同僚に薦めたいと思うか?」という問いに対する答えを、0~10の11段階で調査。10~9をプロモーター(推奨者)、8~7をニュートラル(中立)、6以下をデトラクター(非難者)に分類する。プロモーターが占める%比率からデトラクターが占める%比率を差し引いた%数値をNPS指標とするもの。
一件日本でもよくある5択の質問が11択になっているだけのようにも思われるかもしれませんが、明確にポイントでプロモーター、ニュートラル、デトラクターと分類して、それぞれの傾向を深掘りして対策をしようとPDCAを回す点が大きな特徴でしょう。
実はAMNでも今年からNPSを導入してみているのですが、確かになかなか興味深い結果が出てきます。
顧客のロイヤリティーや満足度の測り方に悩んでいる方はもちろん、ソーシャルメディアの効果測定に悩んでいる方にも参考になる点が多い本だと思います。
「グランズウェル」や「エンパワード 」とあわせて読むのもお勧めです。
【読書メモ】
■悪しき利益と良き利益
顧客とのリレーションシップを犠牲にして得られる利益が悪しき利益なのである
■悪しき利益の悪影響は、そのほとんどが、悪しき利益が作り出す「批判者(デトラクター)」の手によってもたらされる。
あまりのひどさに、こうした顧客は購入額を減らし、可能ならば競合他社に乗り換える。また、そんな思いをさせた企業を避けるよう周囲に警告を発する。
■推薦者(プロモーター)
満足客たちは、実質的にその企業のマーケティング部門の一部となり、みずから購入額を増やすだけでなく、人にも熱心に推奨してくれる。
続きを読む 顧客ロイヤルティを知る究極の質問(フレッド・ライクヘルド) は、NPS(ネットプロモータースコア)を理解するための必読本です。