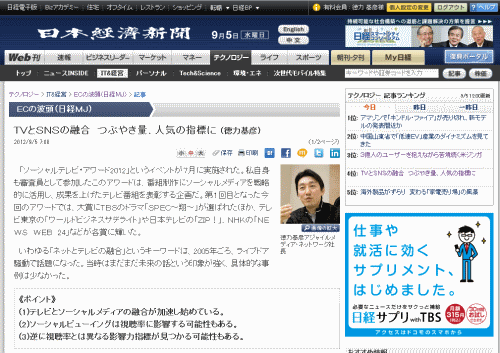ここ最近、ツイッターのAPI騒動の影響で、ツイッターの未来に関する議論が久しぶりに盛り上がっている印象があります。
象徴的なのはこちらの記事でしょう。
・Twitter関連サービスの終了相次ぐ API利用制限など「Twitterの変化」影響

実際にサービスが停止されたと紹介されているサービスは3件ですから、実際のTwitter関連サービスの数を考えると、終了相次ぐ、と言うほど相次いではいないと思うのですが、そういうタイトルをつけたくなる気持ちも分かるぐらい、API変更によるTwitter関連サービスの開発者の反応はネガティブです。
このあたりの事情については、日本を代表するツイッタークライアントであるモバツイの開発者のえふしんさんがコラムを書かれているのでこちらを読んで頂ければと思いますが。
・Twitter API ver1.1利用規約変更から学ぶプラットフォーム時代の生き方【連載:えふしん⑥】 |エンジニアtype
この辺の事情をご存じない方に簡単に説明すると要はこういうことです。
■無名だった頃のツイッターは、APIを大きく開発者に開放してきた。
↓
■それにより、ツイッター社1社では不可能だったと思われるような急速な成長やエコシステムの拡大を実現してきた。
↓
■最近のツイッターは、有名になって会社も大きくなったせいか、急に一部のAPIを制限し、これまで仲間だった開発者を閉め出し始めた。
↓
■閉め出された開発者は当然ショックだし怒る。
まぁ、冷静に第三者の視点から見ると、無名だったアイドルが有名になった途端に無名だった頃に相手をしていたファンの相手をしなくなり、昔からのファンが怒っているという構図にも見えてしまったりするわけで、良くある話ではあるのでしょうが、個人的に気になるのはやはりツイッター社の本質的な変質が起こっているのかどうかです。
続きを読む ツイッターAPI騒動を見ながら、ツイッターは非常識なサービスのままでいるべきか、普通のサービスを目指すべきか改めて考えてみる