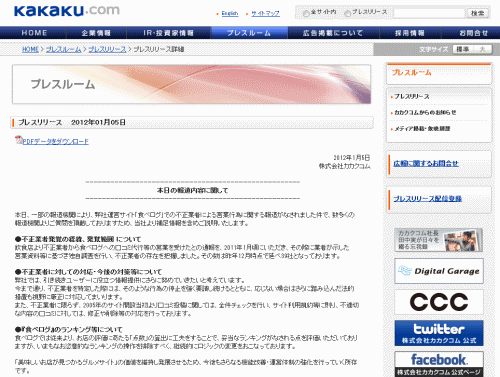「フリー〈無料〉からお金を生みだす新戦略」は、一昨年「フリー」という概念をブレイクさせるきっかけになった書籍です。。
「フリー〈無料〉からお金を生みだす新戦略」は、一昨年「フリー」という概念をブレイクさせるきっかけになった書籍です。。
発売時に献本を頂いていたのですが、書評抜き読書メモを公開するのをすっかり忘れていたので、今更ながら公開させて頂きます。
監修をされた小林さんがよく言っていましたが、「フリー」という言葉が一人歩きした結果、本を読んでいない人が「何でも無料になってしまうんだろ」と勘違いしていたようですが、個人的にもこの「フリー」で最も大事な概念は「フリーミアム」というキーワードだと感じています。
実は無料をエサに、利用者を有料モデルへ誘導していくというビジネスモデル時代はインターネット以前から存在するわけですが、インターネットによりこの無料を大量の人に提供するということが実施しやすくなったのが「フリー」が大きく注目されたポイントでしょう。
現在、このフリーミアムで最も成功している産業は間違いなくソーシャルゲーム業界と言えます。
無料ゲームをうたい、とにかくユーザーをゲームに登録させてしまえば、ほかのユーザーに勝つため、もしくは助けるためにお金を払うことになるというサイクルに、ユーザーを組み込む事ができています。
従来のゲームが、お金を払わって製品を買わなければ面白いかどうかが分からなかったのに比べると対極にあるビジネスモデルと言えるでしょう。
ただ一方で、このコンセプトを理解したところで、どこまでを無料にして、どこからを有料にするかというバランスが実は最も重要で、何でも無料で配ればいいという話ではないのが、このフリーミアムの奥が深いところ。
実はまだまだこれからフリーミアムのコンセプトで革命が起こる業界や分野はいくつもあるのではないかと思います。
一昨年の「フリー」ブームのときに、読みそびれたという方も、今改めて読むのをオススメします。
【読書メモ】
■無制限の商品棚を持つことを可能にする方法はひとつしかない。その商品棚のコストがタダであることだ。
■フリーの4つのビジネスモデル
1・直接的内部相互補助
あるモノを無料かそれに近い値段にし、それで客を呼んで、健全な利益を出せる他の魅力的なモノを売ろうとする。
2・三者間市場
二者が無料で交換をすることで市場を形成し、第三者があとからそこに参加するためにその費用を負担する。
3・フリーミアム
有料のプレミアム版に対して、大量の無料版を提供する
4・非貨幣市場
贈与経済、無償の労働、不正コピー等
■(ラジオによる)フリーは音楽ビジネスを崩壊させることなく、反対に音楽産業を巨大で儲かるビジネスに変えた。
低品質の無料バージョンは、音質のよい有料バージョンを買ってもらうためのすぐれたマーケティング手法となった。
続きを読む フリー〈無料〉からお金を生みだす新戦略(クリス・アンダーソン)で、改めて考える「フリーミアム」の可能性
![]()