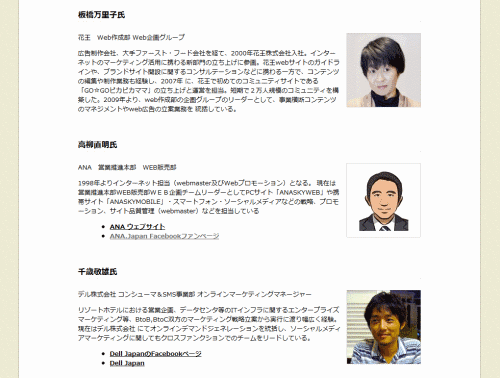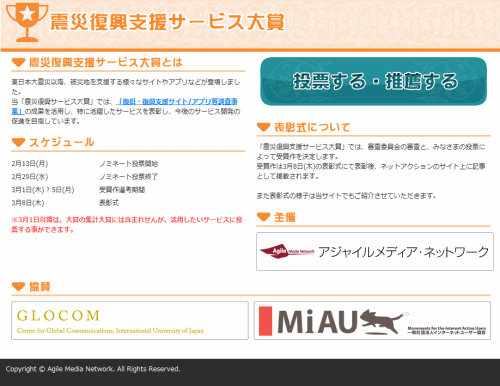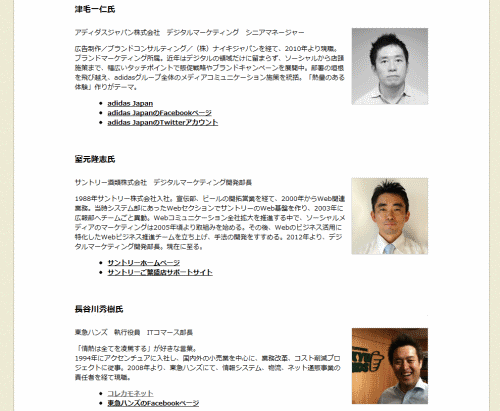「ビジネスで一番、大切なこと」は、 ハーバード・ビジネススクールの人気教授であるヤンミ・ムン氏の書籍です。
「ビジネスで一番、大切なこと」は、 ハーバード・ビジネススクールの人気教授であるヤンミ・ムン氏の書籍です。
他の本を読んだ時に引用されていたので、買って読んでいたのですが遅ればせながら書評抜き読書メモを公開させて頂きます。
タイトルだけ見ると経営者向けの一般教養書のように見えてしまうかもしれませんが、この本の原題は「Different」。メインテーマとなっているのは「差別化のジレンマ」とでもいう現象です。
一般的に他社との競争の過程で、他社商品やサービスとの差別化を意識するあまり、他社の研究をしすぎて結果的に製品やサービスが似通っていってしまう、という著者の指摘は最近のスマートフォン市場やデジタルカメラ市場などの状況を振り返っても非常に納得です。
本来は差別化というのは、他社と異なる存在になろうとする行為のはずですが、他社との違いを出そうとするために他社の特徴を学ぶと、結果的に他社の特徴を自社が備えていないことが不安要素となり、スペック表の上ではすべての項目に○がつくような製品・サービス展開を選択することになりがち。
実は差別化においては、何をやらないか、ということを決めることの方が重要だということに気づかされる書籍です。
製品やサービスの差別化に悩んでいるマーケティング担当者には、刺激になる点が多々ある書籍だと思います。
「リ・ポジショニング戦略」や「独自性の発見」あたりも合わせて読むのもお勧めです。
【読書メモ】
■教師としての実感からいえば、暗唱は能力を高める一方、ある種の惰性をもたらす。多くの教育者が批判するように、頭を使わなくなるのだ。一度覚え込むと、それ以上学ぼうとしなくなる。これが今、ビジネスの世界で起きている現象だ
■ポジショニングマップや市場調査に限らず、どんな分析手法にも言えることだが、自社の競争力を測るという前向きな努力が、結果的には均質化を促すムチになってしまう。
■真の差別化は、均整の取れた状態から生じるものではない。むしろ偏りから生まれる。
■製品の拡張の形
・付加型:よりよく、新しく進化させる。足し算の製品拡張
・増殖型:選択肢が掛け算のごとく増えていく。企業は特定のセグメントのニーズを満たす製品をひねり出す
続きを読む ビジネスで一番、大切なこと (ヤンミ・ムン) を読むと、差別化のジレンマとでも言うべき、他社との競争に集中することの弊害について考えさせられます。