 「プロブロガーのアクセスアップテクニック100」は、コグレさんとするぷさんのプロブロガー本第二弾です。
「プロブロガーのアクセスアップテクニック100」は、コグレさんとするぷさんのプロブロガー本第二弾です。
献本をいただいていたのですが、遅ればせながら書評抜き読書メモを公開させて頂きます。
この本は「必ず結果が出るブログ運営テクニック100」というプロブロガー本第一弾の続編になります。
プロブロガーという言葉を聞くと、シンプルにブログでお金儲けというイメージを持たれる方も多いかもしれませんが、この本で薦めているのは「仲間と収入を目的にしよう」と言う点です。
金銭的なリターンだけを考えると、ブログ以外にもたくさんお金儲けの手法はあると思うんですが、仲間作りと副収入が両立する可能性があるのがブログの一つの面白さだと個人的にも感じていて、そういう視点でこの本は読んで頂くと良いのではないかと思います。
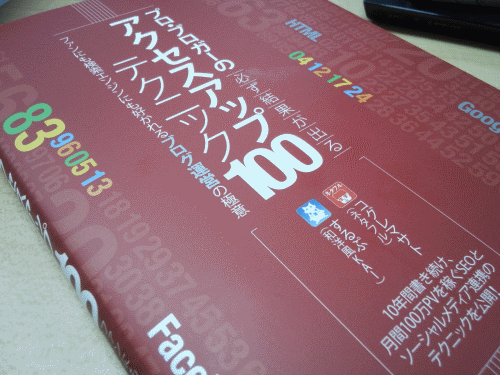
ブロガーサミットの時にも「ブログ書くのってお金目当てでしょ、という誤解をいまだにしている人たちには、今すぐお金欲しいならバイトの方がよっぽど効率良いと、声を大にして言いたい今日この頃。」という記事でも軽く紹介したんですが、コグレさん達の本で強調されているのは常にブログで一番大事なことは「ブログを楽しみながら長く続けることだ」という点です。
タイトルだけ見ると少しハードル高く感じるかもしれませんが、コミュニケーションのためにブログを運営している方にも参考になる点が多い本だと思います。
「必ず結果が出るブログ運営テクニック100」や、「ネットで成功しているのは<やめない人たち>である」と合わせて読むのもお薦めです。
【読書メモ】
■本書でも「仲間と収入を目的にしよう」という基本的な考え方は変わりません。
そのためには数字として見えるひとりひとりに、読んで「おもしろかった」「役に立った」と感じてもらい、ファンになってもらい、いい関係を築くことが大切です。
そして、多くの人との間に関係を築くことを目指しましょう。
■ネガティブな結論にしかならないネタは避ける
月別: 2014年2月
世界が土曜の夜の夢なら ヤンキーと精神分析(斎藤 環)は、最近話題(?)のヤンキー論を理解したい方にオススメです。
 「世界が土曜の夜の夢なら ヤンキーと精神分析」は、サブタイトルにあるように日本における「ヤンキー」について考察されている書籍です。
「世界が土曜の夜の夢なら ヤンキーと精神分析」は、サブタイトルにあるように日本における「ヤンキー」について考察されている書籍です。
さとなおオープンラボで話題になったので買って読んでいたのですが、遅ればせながら書評抜き読書メモを公開させて頂きます。
個人的にも日本におけるネットサービスの傾向を考える上で、ヤンキー論というのは非常に興味深い視点だと考えています。
ヤンキーというと、いわゆるマンガに出てくるような不良少年をイメージする方も多いかもしれませんが、この本で議論されているのは「ヤンキー的なもの」
日本においてブームと呼ばれる現象になるためには、ヤンキー的なものであることが必要であるという観点で、日本の開国の歴史からYOSHIKIや木村拓哉のような芸能人まで様々な視点で分析されています。
誤解を避けずにシンプルに分類すると、ネットサービスにおいてもシリコンバレー的なサービスと、ヤンキー的なサービスと無理矢理わけると、FacebookやGoogle、はてなはシリコンバレー的、アメーバや楽天はヤンキー的という感じになるのかなぁと、それを元に日本におけるネットサービス成功のポイントを議論したりすると朝まで語れてしまったりするのかなと思ったりしています。
その辺はまたブログに書いてみたいと思いますが、とりあえず最近話題になってきたヤンキー論を俯瞰的に考えてみたい方には参考になる点が多い本だと思います。
これを読んでから今改めて「ウェブ進化論」と「ウェブはバカと暇人のもの」を合わせて読むのもオススメです。
【読書メモ】
■できるだけ多くの国民を動員しようと考えるなら、ヤンキー的なものを避けては通れない。それはまぎれもない事実なのだ。
■ヤンキー的なものとは何か。たとえばATSUSHIやYOSHIKIといった独特の表記に注目してみよう。そこには、間違いなく一つの「美学」が刻まれている。そのような美学の総体を、さしあたり「ヤンキー」と呼ぼう。
■おそらく木村拓哉のヤンキー性は、彼が「語る存在」ならぬ「語っちゃうキャラ」を演じ「させら」れている、という点にきわまっている。
続きを読む 世界が土曜の夜の夢なら ヤンキーと精神分析(斎藤 環)は、最近話題(?)のヤンキー論を理解したい方にオススメです。
有料メルマガと、無料のブログやソーシャルメディアの情報発信は、根本的に必要な才能が違うんじゃなかろうか
ここしばらく、有料メルマガのブームが終わったというブログ記事を目にすることが多いので、昔から一度まとめようと思っていた自分の考えを書いておこうと思います。
主な論点は下記の記事にまとまっているので、そちらを見ていただくとして。
・「休刊・廃刊メルマガ特集」を自分で紹介する:渡辺文重の有料メルマガ批評
・2014年メルマガ「ブーム衰退」を振り返る – 乱れなよ、そして召されなよ
象徴的な出来事としてわかりやすいのは、グリーの有料メルマガサービスMagarlyが1年で終了した点でしょうか。
・グリーの有料メルマガ「Magalry」終了 開始から1年余り

まぁ、この辺は本業のソーシャルゲームの動向との兼ね合いもあると思うので、一概に連動した出来事とはいえないかもしれませんが。
何となく2012年頃のブームを考えると、一時期のセカンドライフほどではないものの、ピークと実態の乖離が非常に幅のある結果になってしまった印象はあります。
有料メルマガ自体は、そもそもインターネットの黎明期から存在するビジネスモデルで、目新しいものではありません。
それが2012年の頃にブーム的に注目されたのは、津田さんや堀江さん、やまもといちろうさんなどネット系の著名人による有料メルマガの成功事例が明確に見えてきたからだったと記憶しています。
特に津田さんは、ツイッターのフォロワーが日本トップクラスで注目されていたものの、ブログのGoogle Adsenseのような書き手への収益還元の仕組みがツイッターには存在せず、「ツイッターだけで生きていければ良いのに」と飲み会かどこかでこぼしていたのをぼんやりと覚えています。
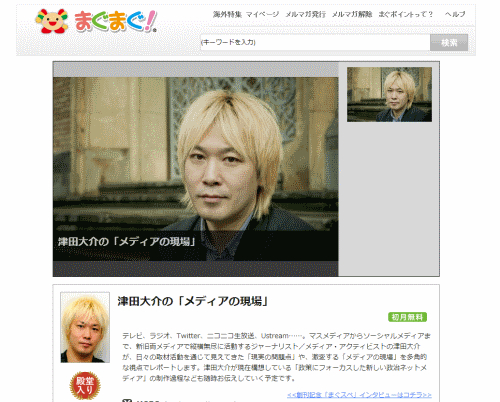
ビッグデータの覇者たち(海部美知)
 「ビッグデータの覇者たち」は、ビッグデータ時代の未来について海部さんが紹介されている書籍です。
「ビッグデータの覇者たち」は、ビッグデータ時代の未来について海部さんが紹介されている書籍です。
献本を頂いていたのですが、遅ればせながら書評抜き読書メモを公開させて頂きます。
昨日ご紹介した「データサイエンティスト」は、ビッグデータ時代における我々個人が必要とされるスキルをテーマにした本ですが、こちらのビッグデータの覇者たちは、俯瞰的視点でビッグデータ時代の未来について考察をされている本です。
特に日本でもよく話題になるビッグデータの可能性の裏側にあるプライバシー問題の実害と気持ち悪いという感覚的な問題について海部さんならではの視点で考察されていますので、一度全体の構造を把握したい方には参考になる点がある本だと思います。
「データサイエンティスト」や「データ・サイエンティストに学ぶ「分析力」」と合わせて読むのもお勧めです。
【読書メモ】
■ビッグデータとは
人間の頭脳で扱える範囲を超えた膨大な量のデータを、処理・分析して活用する仕組み
■ソーシャル+モバイルのチャンネルからクラウドに流入するデータは、究極の有機的データであり、作成者の人間関係・属性・居場所など、あらゆる「プライバシー」要素がてんこもりです。
■究極的にはビッグデータの活用がユーザーのためになる、さらにそれゆえに、コストを下げ、利益を上げることができる
データサイエンティスト (橋本大也)に書かれている基礎知識は、今後のマーケティング担当者の必須の基礎知識になりそうです。
 「データサイエンティスト」は、タイトル通り「データサイエンティスト」の役割や必要な能力について橋本大也さんが紹介されている書籍です。
「データサイエンティスト」は、タイトル通り「データサイエンティスト」の役割や必要な能力について橋本大也さんが紹介されている書籍です。
献本を頂いていたのですが、遅ればせながら書評抜き読書メモを公開させて頂きます。
「データサイエンティスト」というキーワードは、「データ・サイエンティストに学ぶ「分析力」」という本をきっかけに、かなり広告業界でも話題になった言葉といえると思います。
ただ、やはりデータやサイエンティストという言葉から、自分には関係ない別世界での話だと思い込んでしまっている広告業界関係者の方はまだまだ多いように思います。
私自身もデータに対する苦手意識は強いですし、難しいデータの話はなかなか頭に入ってこなかったりするわけですが。
この橋本さんの「データサイエンティスト」では、新書ということもありますし、書評ブロガーとしても有名な橋本さんならではの分かりやすい語り口で、データ分析の基本を教えてくれますので、データに苦手意識の強い広告業界の方やマーケティング担当者の方には、とっつきやすい一冊といえるんではないかと思います。
「データ・サイエンティストに学ぶ「分析力」」はもちろんですが、「グロースハッカー」や「リーン・スタートアップ」と合わせて読むのもお勧めです。
【読書メモ】
■データサイエンティストに必要な3つの能力
・統計とITの能力
・ビジネスの問題を発見し解決する能力
・創造的な提案を行う能力
■平均の取り方
・算術平均
・中央値
・最頻値
■マスメディアが当たり前のように仮定する前提さえ、認知バイアスがかかっていることがある。
続きを読む データサイエンティスト (橋本大也)に書かれている基礎知識は、今後のマーケティング担当者の必須の基礎知識になりそうです。
明日19日17時~のソーシャルメディアウィークの「イジられるブランドになろう!」というセッションに登壇します。 #SMWTOK
すっかり告知が遅くなってしまいましたが、明日19日水曜日の17時から開催されるソーシャルメディアウィークのセッションにパネリストで登壇させて頂きますので、ご紹介です。
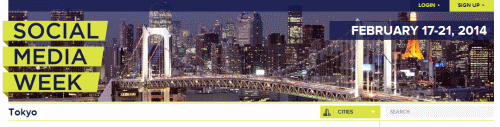
セッションのテーマは「イジられるブランドになろう! ~企業の新しいコミュニケーション戦略」
企業がクチコミで話題にしてもらうためには、イジられ力みたいなものが大事なのではないかと言う、ちょっと変わったテーマのセッションです。
パネリストには、「ダウンタウンDX」などのプロデューサーを担当されている讀賣テレビ名物プロデューサーの西田さんと、「ヤフートピックスを狙え」という書籍でもおなじみの市ケ谷経済新聞編集長の菅野さんが並び、電通の富田さんがモデレーターというメディアの領域が異なるメンバーが並ぶセッションになっています。

個人的にも、どんなセッションになるのか想像できず、今からドキドキしていますが、久しぶりのパネリストなので楽しませていただきたいと思います。
参加される皆さん、明日はよろしくお願いします。
・イジられるブランドになろう! ~企業の新しいコミュニケーション戦略
なお、おそらくUstream配信もされるかと思いますので、こちらもどうぞ。
Video streaming by Ustream