ad:tech Tokyo公式ブログの方でもプレイベントの告知がされていますが、いよいよ、「ad:tech Tokyo」開催まで50日を切ったようです。

わたしもAMNに入った関係で、広告業界の方と情報交換することがこの2年間一気に増えましたが、未来の広告業界を語る上で、必ずといっていいほど出てくる言葉だったのが、この「ad:tech」というキーワード。
正直、最初の頃は何かのサービス名か会社の名前かと勘違いしていたぐらいだったのですが。
世界をまたにかけて開催されているデジタルマーケティングの世界最大規模のイベントだそうで。
すでに7カ国11都市で開催されていると言うから凄いです。
話をいろんな人から聞けば聞くほど、一度参加してみたいという思いは募るのですが、まだ一回も参加することができていません。
そんなad:techが今年はいよいよ東京で開催されるというので、個人的にも楽しみにしているわけです。
で、ad:techについて、先日武富さんに教えてもらうまでもう一つ勘違いしていたのが、そのイベントの開催方法。
世界最大規模のイベントというと、CEATECとかINTEROPみたいに、イベント会社の方が中心になって基調講演とか、パネルディスカッションがトップダウンで配置されていくイメージがあるので、てっきりad:techも主催者の方々が、テーマ毎のパネリストとかファシリテーターをテーマ毎に選んでいくんだと思っていたんですが。
実はパネリストもファシリテーターも公募を基本としていて、そこから主催者がテーマ毎にメンバーを選考していくというボトムアップなスタイルをベースとしているのだそうです。
当然、選考のプロセスでかなりのフィルタにかけられるんでしょうけど、パネルの枠のテーマだけ先に決めて、スピーカーを公募で募集するというのは、日本の通常のビジネス系イベントではまず聞いたこと無いですよね。
ウェブイノベーションサミット(仮)改め、WISH2009のプレゼン枠の公募を開始しました。
先日の「ウェブプレゼン大会の正式名称投票」にご協力頂いた皆さん、ありがとうございました。ご報告が遅くなりましたが、イベント名称は投票の結果「WISH2009」に確定しました。
(何の話かわからないと言う方は、「日本のウェブを盛り上げてくれそうなサービスや端末のプレゼンイベントをやってみませんか?」をご覧下さい。)
「WISH2009」のWISHは、Web Innovation Share の3つの単語の頭文字を取ったもの。
「ウェブ」に関連する、「イノベーション」を興してくれそうなサービスを、みんなで「シェア」する、というコンセプトで開催したいと思っています。

まだ、ロゴについてもlinkerの黒野さんに候補を作って頂いて、ようやく議論を開始したようなところですが、まずはイベント実施日を8月21日(金)に設定し、とにかくイベントの開催に向けて動き出したいと思います。
つきましては、まずは当日のプレゼンに興味がある企業の公募を開始しましたのでご連絡です。
WISH2009でのプレゼンに興味がある方は、下記のフォームよりご登録下さい。
・WISH2009プレゼンテーション応募フォーム
(なお、大企業の方々がプレゼンする場合はプレゼン枠をスポンサーして頂き、個人や小規模ベンチャー企業のプレゼンは無料にするという形で、当日の会場費等をカバーしたいと考えております。スポンサーの詳細についてはこちらの概要資料をご覧下さい。)
また、合わせてWISH2009で、是非この企業のプレゼンをしてもらうべき!という推薦をして頂くためのフォームも開設しました。
・WISH2009プレゼン企業推薦フォーム
自分はプレゼンしないけど、お勧めのサービスや端末があるという方は、是非こちらからお勧めのサービスを登録して下さい。
複数の投票を集めたサービスや、非常に面白いサービスがあった場合は、こちらから直接打診してみたいと思っています。
なお、プレゼン枠とは関係無しに、直接イベントのスポンサーをしてくれる企業や、プレゼントを提供しても良いと言う太っ腹な企業がもしおられましたら、是非ご連絡下さい。
一緒にスポンサーを探してくれる方も大歓迎です。
また、イベントの企画や、当日のイベント運営を手伝っても良いという方は、下記のメーリングリストにご登録下さい。
|
|
| WISH 2009に参加 |
| このグループにアクセス |
情報の文明学 (梅棹忠夫)
 「情報の文明学」は、「情報産業」という言葉の名づけ親として知られる梅棹忠夫氏の書籍です。
「情報の文明学」は、「情報産業」という言葉の名づけ親として知られる梅棹忠夫氏の書籍です。
欲望のメディアの話をしている際に藤代さんに勧められたので買ってみました。
書評抜き読書メモを公開させて頂きます。
40年も前に書かれた論文を中心に構成された本らしいのですが、今読んでもその本質自体は大きく変わっていないことに驚きを感じる本です。
特に個人的には、「一般に、情報産業の提供する商品を、買い手は、その内容をしりもしないで、先に金をだして買うのである」や、「情報氾濫の時代になればなるほど、情報の情報が要求される」というあたりにインターネットにおける情報産業の課題や可能性を改めて感じました。
現在起こっているネットによるメディアのパラダイムシフトの本質を、一度一歩引いて考えてみたいという方には非常に刺激のある本なのではないかと思います。
【読書メモ】
■ラジオもテレビも放送してしまえばおしまいだ。どんなに苦心してうまくつくりあげた番組も、一回こっきり、あとになんにものこらない。(中略)これはひきあうことだろうか
■ある一定時間をさまざまな文化的情報でみたすことによって、その時間を売ることができる、ということを発見したときに、情報産業の一種としての商業放送が成立したのである。
■従来の職業のなかで放送人にいちばんよく似ているのは、学校の先生だと思う。学校の先生は、教育という仕事にひじょうな創造的エネルギーをそそぎこむわけだが、しかし、その社会的効果というものは検証がはなはだ困難である。
■一般に、情報産業の提供する商品を、買い手は、その内容をしりもしないで、先に金をだして買うのである。こういう商品は、ほかにあまりない。
■坊さんのお布施(情報の価格決定方についてひとつの暗示をあたえる現象)
お布施の額を決定する要因は、ふたつあると思う。ひとつは、坊さんの格である。もうひとつは、檀家の格である。
クチコミマーケティングの効果測定についてのセミナーを開催します。
 すいません、長文のブログ記事を書くのに消耗していて、すっかり告知を忘れていました。
すいません、長文のブログ記事を書くのに消耗していて、すっかり告知を忘れていました。
来週の7月8日(水)に第7回 アジャイルメディア・マーケティングセミナーとして、クチコミマーケティングの効果測定について考えるセミナーを開催します。
講師になって頂くのは、Ad Innovatorでお馴染みの織田さんと、WEB広告研究会の代表幹事としても有名なホンダの渡辺さんです。
織田さんは、言わずとしれた米国の最新動向ウォッチャーですから、今月の日経マーケティングで触れられていた米国のクチコミマーケティング業界の効果測定の標準化の動向についてのお話をしていただく予定です。
・Ad Innovator: [お知らせ]7月8日にクチコミ・ソーシャルメディアマーケティングの効果測定についての講演やります
渡辺さんは、下記の記事に見られるように、企業ホームページでの効果測定をながらく続けて来られている自社メディア構築のプロですので、その視点からサイト上での効果測定についてお話し頂く予定です。
・「企業ホームページは21世紀のPOS」2010年に向けたホンダのネット戦略が明らかに:ITpro
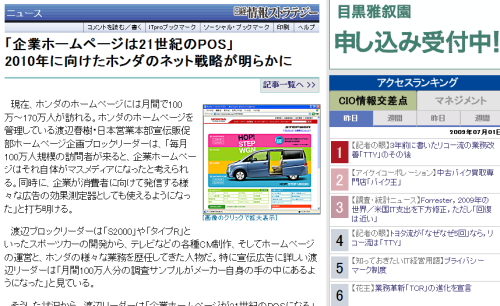 (このインタビューが2006年の段階ですから、凄いです・・・)
(このインタビューが2006年の段階ですから、凄いです・・・)
いわゆる狭い意味でのバズマーケティングやバイラルマーケティング的な”クチコミマーケティング”ではなく、マス広告も組み合わせて巻き起こるクチコミを、様々なツールや企業サイトのアクセス解析でどう効果測定するか、という話になるのではないかと思いますので、興味がある方は是非ご参加下さい。
セミナーの詳細やお申し込みはこちらからお願いします。
・7月8日(水)開催:第7回 アジャイルメディア・マーケティングセミナーのお知らせ
公職選挙法は、Twitterのつぶやきすら違法認定するかもしれない、という日本の現実
昨日は、Twitterと政治のイベントが開催され、今日は先日ご紹介した大柴さんの「YouTube時代の大統領選挙」の出版記念イベントが東急エージェンシーさんで開催され、と、ここ数日は、日本の選挙について考えることが多い一日となりました。

考えてみたら、4月にAMNで開催したネットと選挙をテーマにしたイベントの感想も書いてなかったので、まとめてここにメモしておきたいと思います。
関連記事は、それぞれ下記にまとまっていますので、そちらをご覧いただければと思いますが。
・Twitterは政治や報道を変えるのか (1/2) – ITmedia News
・市民を行動者に変えた、オバマ大統領のソーシャルメディア活用
・AMNブログイベントvol.8「インターネットが選挙を変える? 」
個人的にも、今回のオバマ選挙に影響されて、ネットと選挙のつながりの可能性についていろいろリサーチするようになり、大柴さんのセミナーや、フライシュマンの田中さんの「オバマ現象のカラクリ」やセミナーに影響されて、4月のネット選挙イベント開催にチャレンジしたりしたのですが。
特に4月のイベントで痛感させられたのが、現在の公職選挙法がネットにあたえている影響の大きさ。
公職選挙法は、もともと1950年に制定された法律なのですが、まぁとにかくこのルールがネットの実体にはあっていない模様。
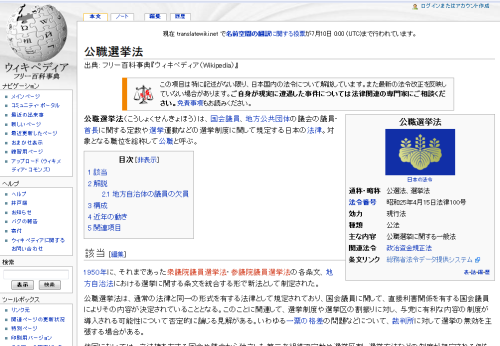
ネットでの書き込み=文書図画の頒布と定義されたことが、とにかくボタンの掛け違いの始まりのようなのですが。
公職選挙法に照らし合わせると選挙期間中は図画の頒布はNGなので、基本的にネットへの書き込みは原則禁止ということになります。
まぁ、4月のイベントで河野太郎さんが言っていたように、仮に候補者自身は忙しくてネットの更新なんかしている暇がないとしても。
個人的に非常に問題と感じているのは、選挙期間中に私たち個人もネットへの書き込みを原則禁じられているに等しいということ。
私のようにブログをコミュニケーションツールとして使っている人間からすると、ブログで選挙について書くことと、居酒屋で選挙について友達と語ることの違いはそれほど大きくないと思うのですが。
法律上は、ブログに書く=文書図画の頒布になるので、私が選挙期間中にブログで候補者や特定の党を褒めたりすることは違法認定される可能性が高いんだそうです。
で、4月のイベントの時には、そうは言っても、きっと何か選挙期間中にもネット上でやれることがあるはずだと思って、いろいろクドイほどパネリストの方々に聞いてみたのですが
驚いたことに、とにかくネット活用は全部ダメなんですよね。
ユニクロの勝部さんに学ぶ、自社に最適なメディアを考えられるのは企業自身ということ
もう既に1ヶ月前の出来事になろうとしているのですが、6月2日に開催された宣伝会議 Internet Marketing & Creative forumに参加しました。
結局、前後の予定の関係で、ユニクロの勝部さんとスターバックスの長見さんのセッションしか参加できなかったのですが、当日のユニクロの勝部さんの発言が非常に印象的だったのでメモしておきたいと思います。
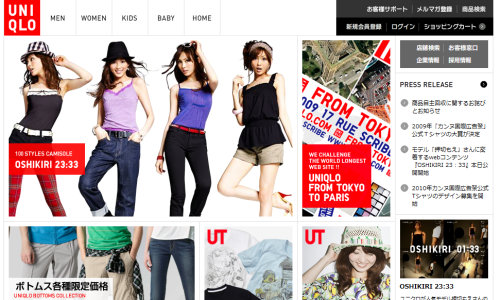
当日の詳細は下記に「マーケター+ジャズ・シンガー」さんが速記録がアップされていますので、そちらをご覧頂くとして。
・宣伝会議 Forum 2009 ユニクロ×スターバックス
個人的に印象的だったのが、勝部さんが「クライアント側が変えなきゃいけない」とか「自分たちでやる」という主旨の発言を繰り返しされていたこと。
なんでもユニクロでは自社の中で、宣伝やCM制作、広報やウェブなどのチームを統合して1つのチームにしてしまったそうで、クリエイティブの制作も自社で低コストで実現する仕組みを構築してしまったんだとか。
そういえば、2月にUNIQLO MEETS CORTEOにご招待頂いたときに、勝部さんにインタビューさせて頂く機会があったのですが、その際にも同じ話をされていたのを思い出しました。

その時はまだピンと来ていなかったんですが、制作チームまで自社で持つというのは改めて聞くと、実に凄いことだと思います。
もちろん、何でもかんでも全て自社でやるのではなく、必要に応じて広告代理店やPR代理店を活用しているんだと思いますが。
広告代理店に提案を持ってきてもらうと、広告代理店の中がマスやウェブなど縦割りの組織になっているので、提案がバラバラに来てしまって統一性が無くなってしまうんだとか。
結局、自社で縦割りの壁を無くして、能力が高くフットワークの良いチームを構築できてしまえば、その方がはるかに効率的と言うことなのでしょう。
まぁ、こうやって書くと年中テレビコマーシャルを打っている広告予算規模の大きいユニクロならではのアプローチという感じを受ける人も多いかもしれませんが。
この姿勢は特にネットを活用したマーケティングを軸にするのであれば、どんな規模の会社でも重要なポイントだと感じています。