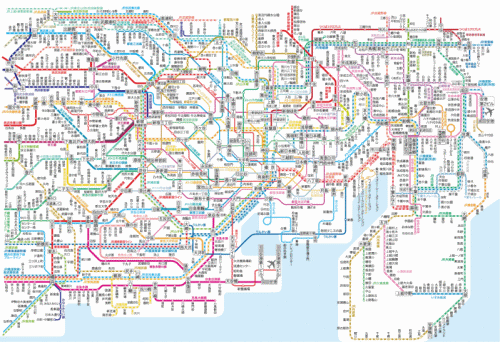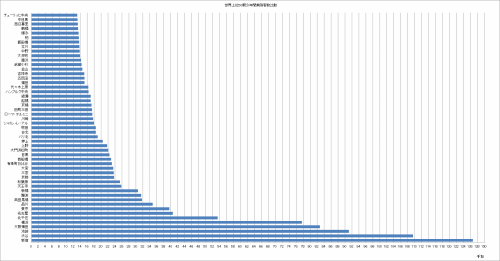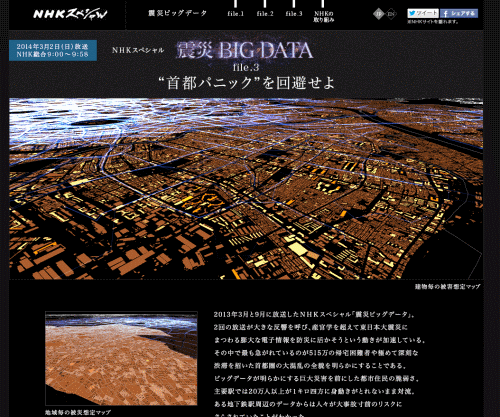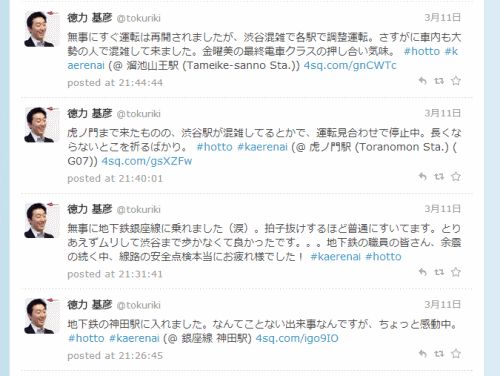「ジェフ・ベゾス果てなき野望」は、Amazon創業者であるジェフ・ベゾスの半生についてまとめられている書籍です。
「ジェフ・ベゾス果てなき野望」は、Amazon創業者であるジェフ・ベゾスの半生についてまとめられている書籍です。
献本を頂いていたのですが、遅ればせながら書評抜き読書メモを公開させて頂きます。
GoogleやYahooなど、ライバルのネット企業に比べると、Amazonというのは不思議なほどインタビュー記事や露出が少ない会社という印象を持っている人は少なくないのではないでしょうか?
実際、ネット企業としての歴史を考えたらAmazonはもっといろんな場面で研究されていてしかるべきだと思うのですが、ECサイトという業態ゆえか、地味な印象すらあります。
ただ、この本を読むと、Amazonやジェフ・ベゾスのイメージが全く変わるという人も多いのではないでしょうか。
ジェフ・ベゾスが比較されるべきは、ラリーペイジやマーク・ザッカーバーグではなく、スティーブ・ジョブズであるべきで。
実際問題、近接する産業において二人はライバルとして比較されるべき存在だったのに、意外なほどにそういう比較が少なかったのが不思議なぐらいと感じられるようになると思います。
「フェイスブック 若き天才の野望」を読んだときにも、アメリカのジャーナリストというのは一冊の本のために本当に丁寧に取材を積み上げるものなんだなぁとつくづく感心しましたが。
この「ジェフ・ベゾス果てなき野望」も、そうした事実に裏打ちされた歴史本として、ネット業界の歴史を考える上での必読本の一冊にあげられるようになるのではないかと思います。
Amazonが何故あれだけ着実に成長できているのか、一歩引いた視点で見てみたい方にはお薦めの一冊です。
「グーグル ネット覇者の真実」や「フェイスブック 若き天才の野望」、そして「スティーブ・ジョブズ」などを合わせて読むのもお薦めです。
【読書メモ】
■「我々は正真正銘、顧客第一ですし、正真正銘、長期的です。」(ジェフ・ベゾス)
■「我々はモノを売って儲けているんじゃない。買い物についてお客が判断するとき、その判断を助けることで儲けているんだ」
続きを読む ジェフ・ベゾス果てなき野望(ブラッド・ストーン)を読むと、Amazonがハンパなく恐ろしい会社であることが痛感できます。