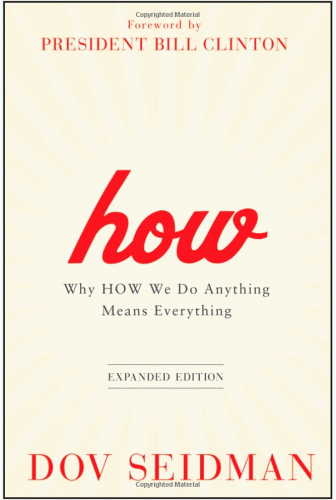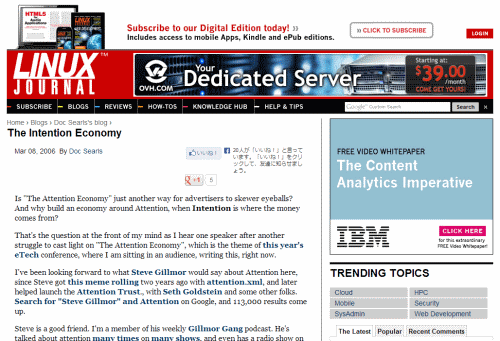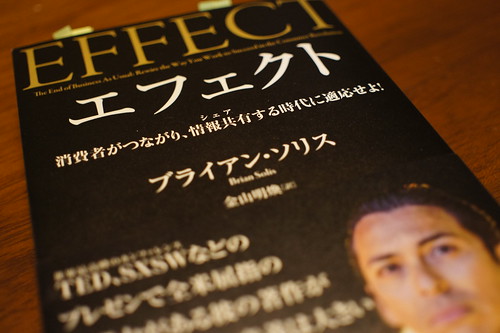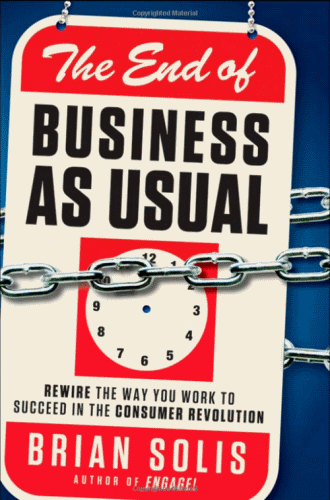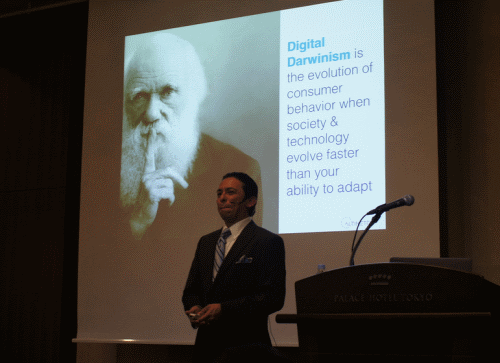「Yコンビネーター シリコンバレー最強のスタートアップ養成スクール」は、起業家養成スクールの火付け役ともいえるYコンビネーターについて書かれている書籍です。
「Yコンビネーター シリコンバレー最強のスタートアップ養成スクール」は、起業家養成スクールの火付け役ともいえるYコンビネーターについて書かれている書籍です。
献本を頂いていたのですが、遅ればせながら書評抜き読書メモを公開させて頂きます。
Yコンビネーターと言えば、IT系のスタートアップ界隈では知らない人はいないと言っても過言ではないぐらい有名な会社。
創設者のポール・グレアム氏は以前にこのブログでも「ハッカーと画家」という書籍を紹介しましたが、シリコンバレーだけでなく世界的なスタートアップのカリスマです。
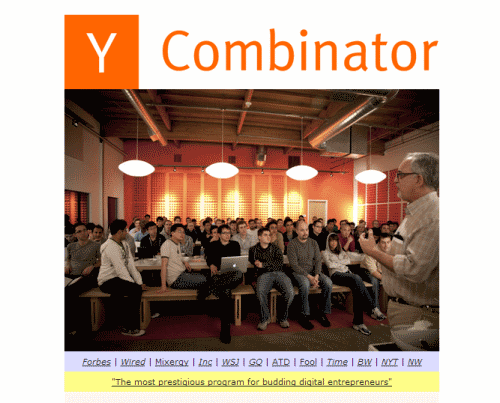
このYコンビネーターという書籍では、そんなポール・グレアムがYコンビネーターの門を叩いた起業家の卵を、どのように叱咤激励し、育てているのか、非常に生々しいタッチで描かれています
日本においてもここ数年、インキュベーターやベンチャーキャピタルがスタートアップ専用のオフィスを開設し、起業家養成スクール形式で起業家を支援する形式が急増しましたが、その起点になっているのはこのYコンビネーターなのは間違いありません。
個人的にはそんなグレアムが「インキュベーターが提供するオフィスに閉じ込められ、息苦しい監視の下におかれては起業家に必須の独立心が窒息させられると信じている。」というスタンスだったというのにはちょっと驚きました。
表面上の起業家養成スクールという形式はコピーできても、ポール・グレアムという魂自体は真似できないわけですから、実は日本の起業家養成スクールと、シリコンバレーのYコンビネーターや500Statupsには細部に大きな違いがあるのかもしれないなと思ったりします。
起業を目指している方だけでなく、新規事業や新サービスに取り組んでいる企業の方々にも刺激になる点がある本だと思います。
「ハッカーと画家」はもちろん、「リーン・スタートアップ」もあわせて読むのがお勧めです。
【読書メモ】
■「スタートアップを始めても多分失敗するだろう。ほとんどのスタートアップは失敗する。それがベンチャー・ビジネスの本質だ。しかし、失敗を受け入れる余裕があるなら、失敗の確率が90%ある事業に取り組んでも判断ミスにはならない。40歳になって養わなければならない家族がある状態での失敗は深刻な事態になる。しかし君たちは22歳だ。失敗してもそれがどうした?」(ポール・グレアム)
■「25歳はスタミナ、貧乏、根無し草性、同僚、無知といった起業に必要なあらゆる利点を備えている」
■最新のテクノロジーを利用しようとする起業家が迫られる選択
・一般ユーザー向けにプロダクトを提供するか(自身で金を採るか)
・一般ユーザー向けにプロダクトを開発しているデベロッパー向けにソフトウェア・ツールを売るか(ツルハシを売るか)
続きを読む Yコンビネーター シリコンバレー最強のスタートアップ養成スクール を読むと、起業やスタートアップに対する考え方が根本的に変わるかもしれません。